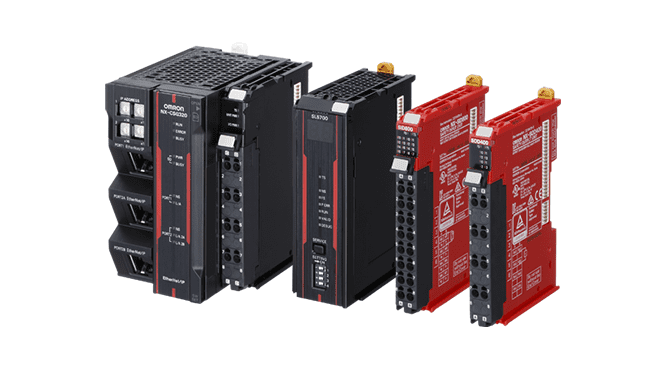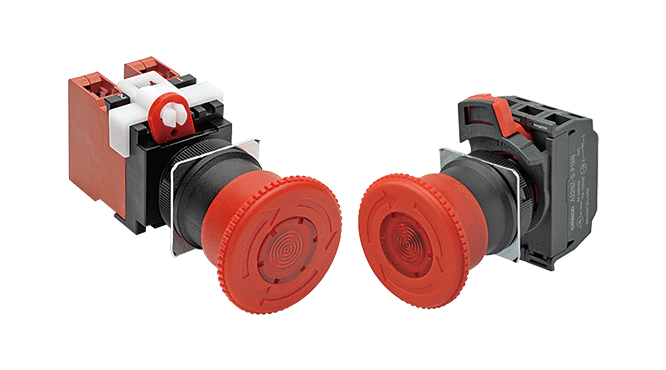更新日:2018.02.13
協働ロボットに関するTS(標準仕様書)が発行されました
産業用ロボットの安全規格「JIS B 8433シリーズ」の関連文書として、協働ロボットに関する要求事項を補完する標準仕様書*1「TS B 0033」が発行されました。
TS B 0033:2017(ISO/TS 15066:2016)ロボット及びロボティックデバイス - 協働ロボット
このTS B 0033は、ISO/TS 15066:2016に対応したものとして2017年11月に公表されたものです。JIS B 8433-1(ISO 10218-1)における協働運転用ロボットの要求事項を満たしたロボットを用いて、JIS B 8433-2(ISO 10218-2)に基づく協働ロボットシステムを安全に構築する際のガイダンスとして使用できるものとして作成されています。
協働ロボットや協働ロボットシステムに関する用語は、JIS B 8433シリーズおよびTS B 0033にて以下のように定義されています。
- 協働ロボット(collaborative robot):
- 規定された協働作業空間で,人間と直接的な相互作用をするように設計されたロボット。(JIS B 8433-2:2015 3.2)
- 協働運転(collaborative operation):
- 意図的に設計されたロボットが,協働作業空間内でオペレータと作業する状態。(TS B 0033:2017 3.1)
- 協働作業空間(collaborative workspace):
- 生産作業中にロボットシステム(ワークを含む。)と人間とが,同時に作業を遂行できる作業空間内の空間。(TS B 0033:2017 3.3)
協働ロボットは、オペレータと作業空間を共有しながら運転することを目的として作られるロボットです。作業空間を共有するということは、その空間内で稼働するロボットとオペレータとの衝突が容易に考えられることから、協働ロボットの運転中のオペレータの安全確保のためには、あらかじめ設定した協働作業空間をベースとした詳細なリスクアセスメントの実施が必要となります。
日本において、産業用ロボットとオペレータとの協働運転が可能となったのは、2013年12月に労働安全衛生規則第150条の4の施行通達が一部改正されたことによるものですが、同施行通達においても、協働運転ができる条件としてリスクアセスメントの実施を求めています。加えて、協働運転を実施する際のリスクアセスメント実施時の留意事項の一つとして、ロボットの力や運動エネルギーにも言及しています。今回のTS B 0033は、それらのリスクの見積のための指針として活用できる*2と考えられます。
またTS B 0033では、協働ロボットシステムの具体的なアプリケーションについての技術的仕様が述べられています。中でも、協働運転を実現するための安全手法としてJIS B 8433-2で規定されていた「安全適合監視停止」「ハンドガイド」「速度及び間隔監視」「動力及び力制限」のそれぞれについて具体的な設計要求事項が示されていることから、協働ロボットシステムの安全設計を検討する際の参考書として今後の活用が期待されます。
*1. 標準仕様書(TS)とは、JIS制定へのコンセンサスがまだ十分に得られていないものの将来制定の可能性があると判断されて公表されるものです。ISOにおけるTS(Technical Specification)制度と同じ趣旨に基づくものとして、2003年よりJIS制度に導入されています。
*2. 「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正に当たっての留意事項について」(平成25年12月24日、基安安発1224号第1号)として通知された文書内に、「産業用ロボットのマニプレータ等の力及び運動エネルギーについては、国際標準化機構(ISO)の産業用ロボットの規格の技術仕様書(TS15066)において、人に危害を加えないと判断される数値を審議中であること。本技術仕様書が制定され、制御によらず構造的に当該数値以下となることが担保される場合、この観点において危険の生ずるおそれが無いと判断できる一例となること。」と記載されています。