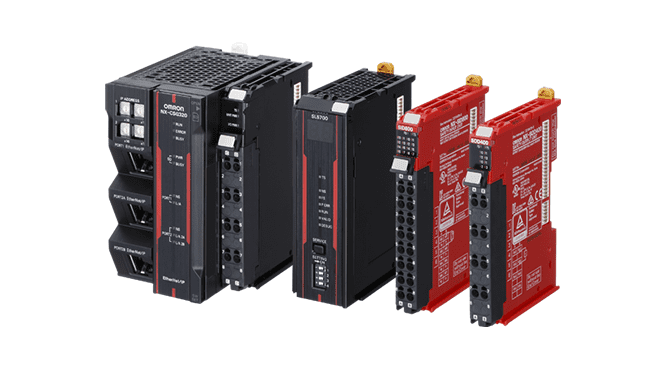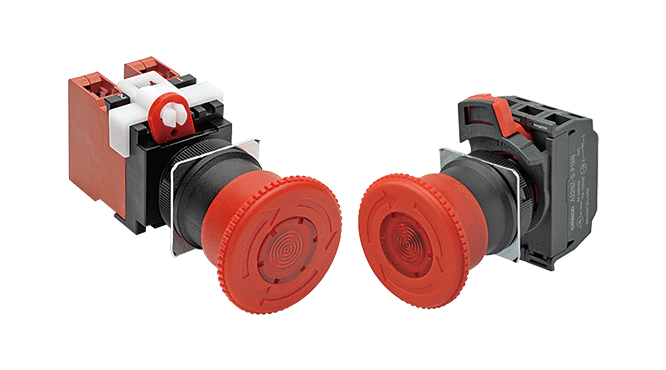日本
労働安全衛生法
日本の労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成する目的で制定された法律です。2006年の改正・施行により「危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施」が必要となりました。これは事業場において危険性・有害性をもつものを特定してそれぞれのリスクを評価し、その評価結果に基づきリスクの低減措置を実施するというものであり、ISO 12100 (JIS B 9700)におけるリスクアセスメントおよびリスク低減方策の実施と同様の内容です。
労働安全衛生規則
労働安全衛生規則においては、すべての機械を対象とした一般基準が定められています。また、工作機械、木材加工用機械、食品加工用機械、プレス機及びシャー、遠心機械、粉砕機及び混合機、ロール機等、高速回転体、産業用ロボットには個別の危険防止基準が規定されています。2013年10月に改正された項目の1つには、すべての機械を対象に、目詰まり等の調整作業時に機械を停止しなければならないことが要求されました。
機械の包括的な安全基準に関する指針
厚生労働省によって2007年7月に改正発行された「機械の包括的な安全基準に関する指針」では、製造者側でのリスク低減の手順を規定し、生産設備・機械類の製造に関して安全性を配慮した設計であることを求めています。さらに、設備導入を行い使用する事業者側にも作業上の安全方策を求めています。
一般に機械の安全性を確保するための安全方策は、製造者側が設計段階で組み込む方策と使用者側が実施すべき方策との組み合わせで構成されますが、製造者側が設計段階で組み込む安全方策は常に機械の使用者側が実施する方策に先行して実施されなければならないことが明確化されています。
「機械の包括的な安全基準に関する指針」による機械の安全化の流れは下図のとおりです。ここで示されている手順は、ISO 12100 (JIS B 9700)におけるリスク低減プロセスとも合致しています。
機械の安全化手順

*1. 指針では、「リスクアセスメント」は「危険性又は有害性等の調査」と表記されています。
*2. 指針では、「危険源」は「危険性又は有害性」と表記されています。
JIS
JISはJapanese Industrial Standards(日本産業規格)の略称であり、日本の国家規格を指す名称です。世界的な貿易の自由化のためには、貿易上の技術的障害を取り除き、各国の規格・基準を国際規格と整合させることは必要不可欠な条件となってきます。このため日本はWTO(世界貿易機構)発効を受けて、TBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)を含めたWTO協定を1995年に批准・加盟し、世界規模での協力体制を宣言しています。その結果、ISO/IECなどから発行される国際規格との整合化をはかったJISが発行されています。
機械安全に関連する主なJIS規格
| 日本工業規格(JIS) | 対応国際規格 | |
|---|---|---|
| JIS B 9700:2013 | 機械類の安全性 ー 設計のための一般原則 ー リスクアセスメント及びリスク低減 | ISO 12100:2010 |
| JIS B 9703:2019 | 機械類の安全性 ー 非常停止機能 ー 設計原則 | ISO 13850:2015 |
| JIS B 9705-1:2019 | 機械類の安全性 ー 制御システムの安全関連部 第1部:設計のための一般原則 | ISO 13849-1:2015 |
| JIS B 9705-2:2019 | 機械類の安全性 ー 制御システムの安全関連部 第2部:妥当性確認 | ISO 13849-2:2012 |
| JIS B 9709-1:2001 | 機械類の安全性 ー 機械類から放出される危険物質による健康へのリスクの低減 第1部:機械類製造者のための原則及び仕様 | ISO 14123-1:1998 |
| JIS B 9709-2:2001 | 機械類の安全性 ー 機械類から放出される危険物質による健康へのリスクの低減 第2部:検証手順に関する方法論 | ISO 14123-2:1998 |
| JIS B 9710:2019 | 機械類の安全性 ー ガードと共同するインターロック装置 ー 設計及び選択のための原則 | ISO 14119:2013 |
| JIS B 9711:2002 | 機械類の安全性 ー 人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま | ISO 13854:1996 |
| JIS B 9712:2006 | 機械類の安全性 ー 両手操作制御装置 ー 機能的側面及び設計原則 | ISO 13851:2002 |
| JIS B 9713-1:2004 | 機械類の安全性 ー 機械類への常設接近手段 第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択 | ISO 14122-1:2001 |
| JIS B 9713-2:2004 | 機械類の安全性 ー 機械類への常設接近手段 第2部:作業用プラットフォーム及び通路 | ISO 14122-2:2001 |
| JIS B 9713-3:2004 | 機械類の安全性 ー 機械類への常設接近手段 第3部:階段、段ばしご及び防護さく(柵) | ISO 14122-3:2001 |
| JIS B 9713-4:2004 | 機械類の安全性 ー 機械類への常設接近手段 第4部:固定はしご | ISO/FDIS 14122-4:2002 |
| JIS B 9714:2006 | 機械類の安全性 ー 予期しない起動の防止 | ISO 14118:2000 |
| JIS B 9715:2013 | 機械類の安全性 ー 人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め | ISO 13855:2010 |
| JIS B 9716:2019 | 機械類の安全性 ー ガード ー 固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項 | ISO 14120:2015 |
| JIS B 9718:2013 | 機械類の安全性 ー 危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離 | ISO 13857:2008 |
| JIS B 9960-1:2019 | 機械類の安全性 ー 機械の電気装置 第1部:一般要求事項 | IEC 60204-1:2016 |
| JIS B 9961:2008/A1:2015 | 機械類の安全性 ー 安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全 | IEC 62061:2005/A1:2012/A2:2015 |
| JIS B 9704-1:2015 | 機械類の安全性 ー 電気的検知保護設備 第1部:一般要求事項及び試験 | IEC 61496-1:2012 |
| JIS B 9704-2:2017 | 機械類の安全性 ー 電気的検知保護設備 第2部:能動的光電保護装置を使う設備に対する要求事項 | IEC61496-2:2013 |
| JIS B 9704-3:2011 | 機械類の安全性 ー 電気的検知保護設備 第3部:拡散反射形能動的光電保護装置に対する要求事項 | IEC 61496-3:2008 |
| JIS B 9706-1:2009 | 機械類の安全性 ー 表示、マーキング及び操作 第1部:視覚、聴覚及び触覚シグナルの要求事項 | IEC 61310-1:2007 |
| JIS B 9706-2:2009 | 機械類の安全性 ー 表示、マーキング及び操作 第2部:マーキングの要求事項 | IEC 61310-2:2007 |
| JIS B 9706-3:2009 | 機械類の安全性 ー 表示、マーキング及び操作 第3部:アクチュエータの配置及び操作に対する要求事項 | IEC 61310-3:2007 |
| JIS C 0508-1:2012 | 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 第1部:一般要求事項 | IEC 61508-1:2010 |
| JIS C 0508-2:2014 | 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 第2部:電気・電子・プログラマブル電子安全関連系に対する要求事項 | IEC 61508-2:2010 |
| JIS C 0508-3:2014 | 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 第3部:ソフトウェア要求事項 | IEC 61508-3:2010 |
| JIS C 0508-4:2012 | 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 第4部:用語の定義及び略語 | IEC 61508-4:2010 |
| JIS C 0508-5:2019 | 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 第5部:安全度水準決定方法の事例 | IEC 61508-5:2010 |
| JIS C 0508-6:2019 | 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 第6部:第2部及び第3部の適用指針 | IEC 61508-6:2010 |
| JIS C 0508-7:2017 | 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 第7部:技術及び手法の概観 | IEC 61508-7:2010 |
(2021年12月現在)