変位センサ/測長センサ 用語解説
変位センサは、対象物までの距離を測定するセンサで、対象物の微小段差や高さ、幅、厚みなどの寸法計測も可能です。測長センサは、対象物が帯状のレーザ光をしゃ光する際の光量変化をとらえ、物体の幅や位置の測定、外径判別を行うセンサです。ここでは、変位センサ、測長センサの用語を解説します。
●分解能
測定対象物およびセンサが静止している状態での、測定値のばらつきの幅を分解能といいます。このばらつきの幅が小さいほど、分解能が良い(高い)といいます。
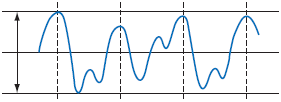
●フルスケール(F.S.)
測定範囲のことです。
例えば、測定範囲±10mmのセンサのフルスケールは20mmとなります。
●直線性(リニアリティ)
リニア出力の理想直線に対する誤差のことです。
通常、測定範囲(フルスケール:F.S.)に対する比率で、1%F.S.…のように表現します。
例)
リニアリティ±0.2%F.S.
F.S.=20mm(測定範囲 30mm~50mm)の場合、誤差を寸法で換算すると、
±0.2×1/100×20=±40μm
となります。
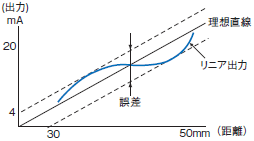
●温度特性
周囲温度の変化に対するリニア出力の変動量です。
通常、測定範囲(フルスケール:F.S.)に対する比率で、□%F.S./℃のように表現します。
例)
0.03%F.S./℃(F.S.=20mm)
この場合、1℃あたりの温度変化に対してのリニア出力の変動量は、
±0.03×1/100×20=±6μm
となります。
周囲温度が23℃から55℃に変化した場合は、
±6×(55-23)=±192μm
となります。
●リニア出力(アナログ出力)
計測結果を電流または電圧に変換して出力することをいいます。
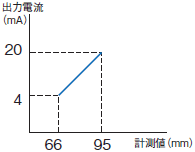
●応答時間
物体の変位や幅がステップ上に変化したときのリニア出力において、アナログ出力では10~90%まで変化するために要した時間を「応答時間」で表現します。
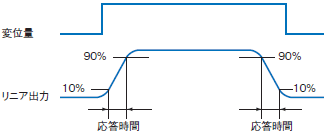
●受光素子
光(レーザ光)を信号として認識するための素子をいいます。
受光素子には、PSD(Position Sensitive Device)、撮像素子(CCD(Charge Coupled Device)、 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor))などがあります。
●静止分解能
対象物、センサが静止しているときの測定値のばらつきの幅のことです。
おもにセンサやコントローラの内部的なノイズなどによるゆらぎが影響して発生します。
●移動分解能
平坦な対象物またはセンサ自身を移動させたときの測定値のばらつきの幅のことです。
移動計測中の検出物体の表面状態によるゆらぎが影響して発生します。
表面が均一で滑らかな物体(鏡やガラスなど)では、移動分解能は小さくなり、静止分解能に近い値が計測できます。また、表面が粗い物体(散乱ワーク)や、レーザ光の反射量を変動させる表面を持つ物体(染み込みワーク)では、移動分解能は大きくなります。移動分解能は、静止状態と比較すると、対象物によっては10倍またはそれ以上に分解能が低下します。
●インピーダンス
回路に交流電流を流したときに生じる抵抗(交流抵抗)をいいます。
-
 PDF版をダウンロード 2641KB
PDF版をダウンロード 2641KB
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.




 マイカタログに追加
マイカタログに追加 Facebook
Facebook