 技術解説
技術解説
-
 コントロール
コントロール
- 温度調節器(デジタル調節計)
-
 タイマ/タイムスイッチ
タイマ/タイムスイッチ
-
 カウンタ
カウンタ
-
 カムポジショナ
カムポジショナ
-
 デジタルパネルメータ
デジタルパネルメータ
-
 信号変換器
信号変換器
-
 通報装置
通報装置
温度調節器(デジタル調節計) トラブルシューティング
温度調節器とは、センサ信号と目標値を比較し、その偏差に応じて演算を行いヒータなどを制御する装置です。センサ信号に温度以外の湿度・圧力・流量などを扱うことができる装置は調節計と呼び、電子式のものを特にデジタル調節計と呼びます。ここでは、温度調節器(デジタル調節計)のトラブルシューティングを説明します。
| トラブルシューティング | |
故障かな?とおもったら、まずご確認ください
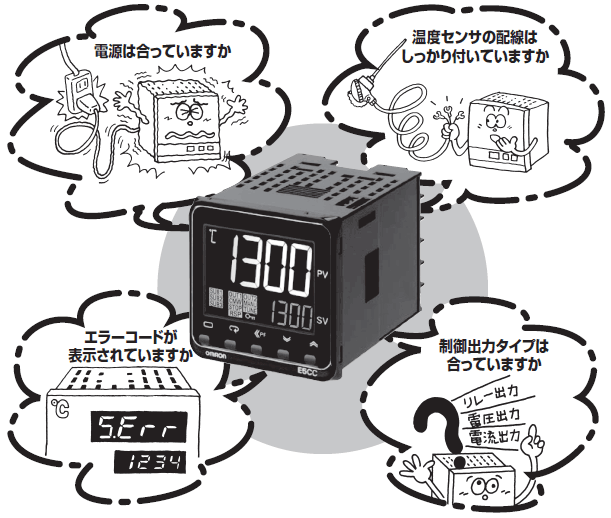
エラーコード表
| 第1表示 | 異常内容 | 処置 |
 | 入力異常 * | 入力の誤配線、断線、短絡および入力種別を 確認してください。 |
 | メモリ異常 | まず、電源を入れ直してください。 表示内容が変わらない場合は修理が必要です。 正常になった場合はノイズの影響が考えられるので、 ノイズが発生していないか確認してください。 |
 | ADコンバータ 異常 * | 内部回路に異常があります。 まず電源を入れ直してください。表示内容が変わらな い場合は修理が必要です。正常になった場合はノイズ の影響が考えられるので、ノイズが発生していないか 確認してください。 |
 | 表示範囲 オーバー * | エラーではありませんが、制御可能範囲であっても 表示範囲を超えたときに表示されます。 ・−1999(−199.9)より小さいとき  ・9999(999.9)より大きいとき  |
 | ||
 | ヒータ断異常 * | まず電源を入れ直してください。 表示内容がかわらない場合は修理が必要です。 正常になった場合はノイズの影響が考えられるので、 ノイズが発生していないか確認してください。 |
*表示が「現在値」または「現在値/目標値」、「現在値/操作量」の場合、エラー表示します。他の状態ではエラー表示しません。
[動作確認方法]
●熱電対での使用時
入力端子を短絡すると室温が表示されます。
●測温抵抗体での使用時
入力端子に抵抗を接続し、温度表示を確認します。
Pt(白金測温抵抗体)の場合100Ωで0℃、140Ωで約100℃が表示されます。
それでもおかしければ、現在温度の動きをみて現象を分けてください。
| 分類 | 項目 | 特徴的波形 |
| A | 温度が上昇しない。 | 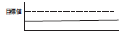 |
| B | 温度が目標値を超えて上昇する。 | 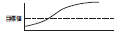 |
| C | オーバーシュート、アンダーシュートする。 | 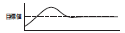 |
| ハンチングする。 | 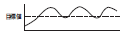 | |
| D | 温度誤差が大きい。 |  |
[A]温度が上昇しない。
1.温調器の初期設定レベルを確認します。
●正動作の設定になっている → 逆動作にする。(加熱制御)
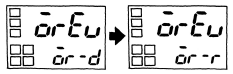
2.温度センサが正しく取りつけられていますか。
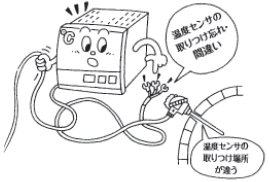
3.ヒータ、周辺機器への接続、動作を確認してください。
●ヒータの断線、劣化が発生している。
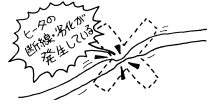
●出力量100% → ●ヒータの加熱容量は充分ですか。
●冷却系が働いていませんか。
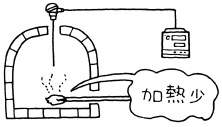
●周辺機器の加熱防止用機器が作動している。
→ <対策>加熱防止温度設定を温調器の目標値より高く設定する。
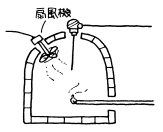
4.SPランプ機能が働いているので制御開始時にヒータがなかなか温まらない。
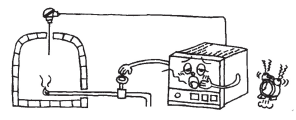
[B]温度が目標値を超えて上昇する。
1.温調器の出力表示とヒータの動作が同じかを確認します。
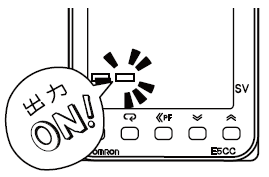
●制御出力の配線が違う。
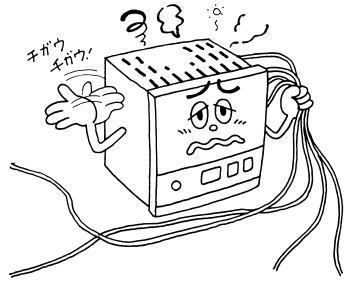
●制御出力リレーの動きと温調器の出力(LED表示)が違う。
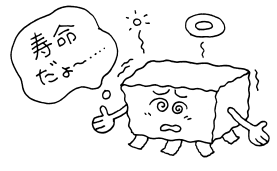
2.温調器の出力とヒータ、周辺機器との接続条件を確認します。
●出力形態が違う。
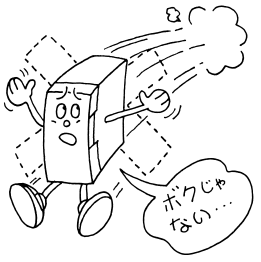
●SSRの動作不良
→ <対策>漏れ電流での動作が考えられる場合は、ブリーダ抵抗をつけてください。
3.オーバーシュートの可能性があります。
PID定数を確認してください。
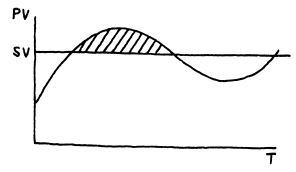
[C]オーバーシュート、アンダーシュートまたはハンチングする。
1.制御方法は適切ですか。
●ON/OFF制御を選択している。
→ PまたはPID制御で一般的に押えられます。
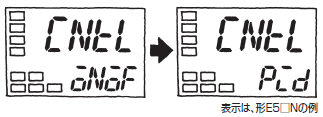
●温度上昇、下降の速さに比べ制御周期が長い。
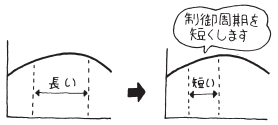
2.PID定数の値は適切ですか。
●デフォルト値で運転している
(工場出荷時の値)
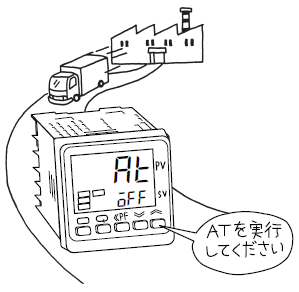
●PID定数の確認をしてください。
[D]温度誤差が大きい。
1.温度センサの入力種別が合っていますか?(温度センサの種別の設定)
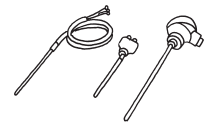
2.温度センサのリード線と動力線を同一配管して引き回しているので
動力線からのノイズの影響を受けている。
(一般的には表示値がふらつく)
<対策>別配線にする。または、引き回しを少なくする。
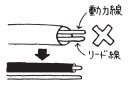
3.温調器と熱電対の間を銅線で接続している。
<対策>熱電対のリード線を直接接続するか、または熱電対に合った補償導線で接続する。
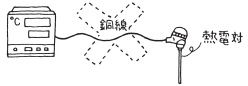
4.温度センサの測温場所が適切か確認をしてください。
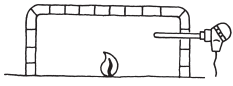
5.入力補正値が設定されていませんか?

入力補正パラメータの値をご確認ください。
トラブル対応フロー(形E5□N-H/形E5□C)
制御出力しない
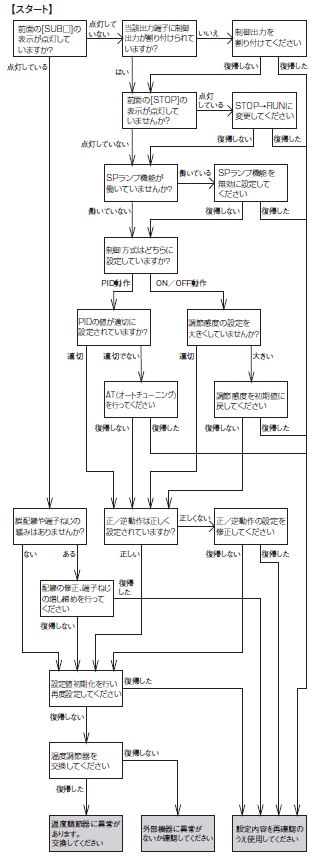
S.ERR(入力異常)表示が出る
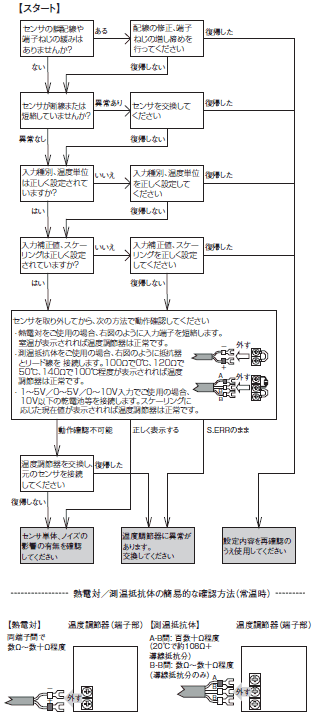
警報出力しない
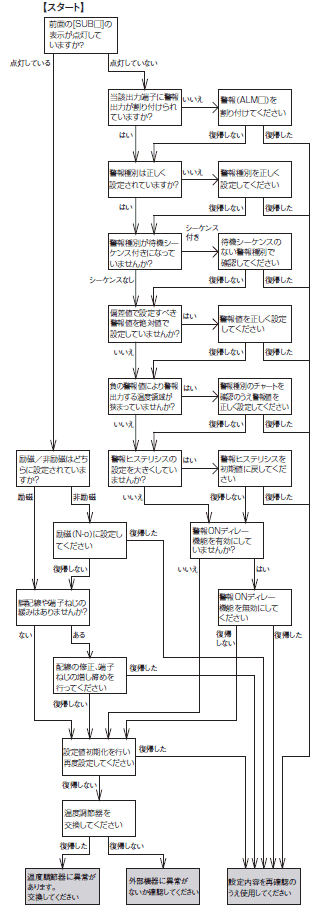
警報出力したままとなる
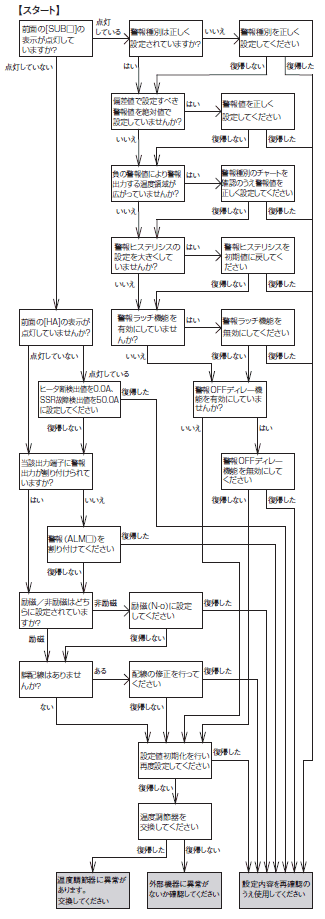
-
 PDF版をダウンロード 6930KB
PDF版をダウンロード 6930KB
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.




 マイカタログに追加
マイカタログに追加 Facebook
Facebook