 技術解説
技術解説
-
 コントロール
コントロール
- 温度調節器(デジタル調節計)
-
 タイマ/タイムスイッチ
タイマ/タイムスイッチ
-
 カウンタ
カウンタ
-
 カムポジショナ
カムポジショナ
-
 デジタルパネルメータ
デジタルパネルメータ
-
 信号変換器
信号変換器
-
 通報装置
通報装置
温度調節器(デジタル調節計) 用語解説
温度調節器とは、センサ信号と目標値を比較し、その偏差に応じて演算を行いヒータなどを制御する装置です。センサ信号に温度以外の湿度・圧力・流量などを扱うことができる装置は調節計と呼び、電子式のものを特にデジタル調節計と呼びます。ここでは、温度調節器(デジタル調節計)の用語を解説します。
制御に関する用語
●調節感度
ON/OFF制御では目標値でON、OFFするので、目標値付近で微小なノイズが入ると出力が頻繁にON、OFF(チャタリング)し、出力リレーの寿命が短くなったり、接続された機器に悪影響を与えます。これを防ぐため、ON、OFFの動作にすきま(ヒステリシス)を設けています。この動作すきまを調節感度といいます。
調節感度(逆動作)
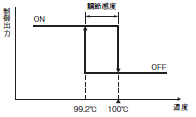
(例)調節感度=0.8℃です。
調節感度(正動作)
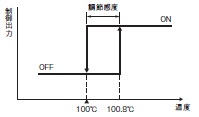
(例)調節感度=0.8℃です。
●オフセット
比例動作では制御対象の熱容量、ヒータ容量により安定状態に達しても、目標値に対して一定の誤差を生じます。この誤差をオフセットと呼びます。このオフセットは目標値の上方に生じる場合もあります。
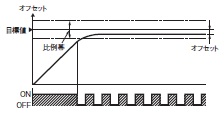
●ハンチングとオーバーシュート
ON/OFF動作時にはよく図に示すような波形が発生します。
この図にみられるように、動作開始後目標値に達したのち行き過ぎる現象のことをオーバーシュート、また目標値のまわりで振動する現象のことをハンチングといいます。この現象が小さいほど、良い制御といえます。
ON/OFF動作におけるハンチングとオーバーシュート
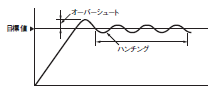
●時分割比例動作
リレー、SSRはON(100%)/OFF(0%)しか出力することができません。しかしPID制御は0~100%の操作量を出力します。時分割比例動作は操作量に時間のパラメータ(制御周期)を加え、ON/OFFの出力で0~100%の出力を可能にした出力方式です。制御周期(秒)×操作量(%)の間出力をONし、残りの制御周期の間出力をOFF することにより0 ~100%の中間の操作量を出力することができます。出力は制御周期の間に1回しかON/OFFしないため、制御周期が長いと制御の応答は遅くなり、制御周期が短いと応答は速くなります。制御周期が短いとリレーなどの接点を持つ出力機器では寿命が短くなります。一般的にリレー出力では制御周期を20秒、SSR出力では制御周期は2秒を目安に設定します。
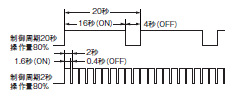
●比例帯
比例帯は制御が比例動作を行う範囲を設定するパラメータです。比例動作は、現在値が比例帯内に入ると目標値と現在値の偏差に比例した0~100%の操作量を出力します。加熱制御では現在値が低い方に比例帯から外れると100%、高い方に比例帯から外れると0%操作量を出力します。
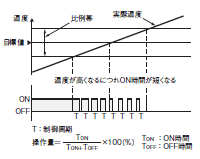
(例)制御周期が10秒で操作量が80%のとき、出力のON 時間およびOFF 時間は次のとおりです。
TON:8(秒)
TOFF:2(秒)
●微分時間
微分動作単体で制御に用いられることはありません。比例動作と同時に制御に用いられます。比例動作と微分動作を組み合わせた制御動作をPD動作と呼びます。PD動作において図のようにランプ状の偏差(一定の勾配で変化する偏差)を与えたとき、微分の操作量が比例動作と同じ操作量に達するまでの時間を微分時間といいます。したがって、微分時間が長いほど微分動作による訂正が強いことを示します。
PD動作と微分時間
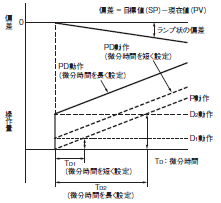
●積分時間
比例動作と積分動作を組み合わせたPI動作、または比例、積分および微分動作を組み合わせたPID動作において、図のようにステップ状の偏差を加えたとき、積分の操作量が比例動作と同じ操作量に達するまでの時間を積分時間といいます。したがって、積分時間が短いほど積分動作は強くなります。しかし、積分時間をあまり短くしすぎると訂正動作が強すぎてハンチングが生ずる原因となることもあります。
PI動作と積分時間
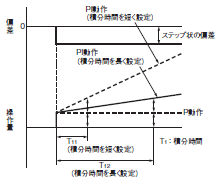
●定値制御
固定の目標値に対し制御します。
●プログラム制御
プログラムに従い時間ごとに変化する目標値に対し制御します。
●オートチューニング(AT)
良好な温度制御を行うことができるPID定数は制御対象の特性により異なります。異なる特性の制御対象に対し適切なPIDを導き出す方法をオートチューニングといいます。代表的な手法としては、ステップ応答法、リミットサイクル法があります。
●ステップ応答法
操作量100%をステップ状に出力し、制御対象の応答から最大温度傾斜(R)とむだ時間(L)を計測し、RとLの値よりPID定数を算出します。
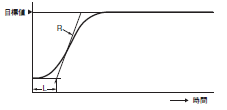
●リミットサイクル法
100%と0%の操作量を交互に出力して制御対象に発生するハンチングの周期と振幅の値からPID定数を算出します。
一般的にオートチューニングというと、リミットサイクル法を指します。
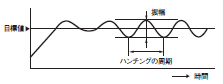
●PID定数の再調整
オートチューニングで算出したPID定数で、ほとんどの場合問題なく制御できます。しかし、アプリケーションによってはオーバーシュート抑制、応答速度改善、安定性向上の優先順位が異なる場合があります。そのときは以下の例を参考にPID定数のそれぞれの値を個別に調整して期待する応答に近付けるように調整することができます。
P(比例帯)を変化させたときの応答
| 大きくすると | 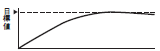 | ゆっくりと立ち上がり整定時間が長くかかりますがオーバーシュート しないようになります。 |
| 小さくすると | 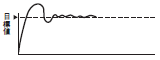 | オーバーシュートが起こりハンチングもありますが早く目標値に到達し、 安定します。 |
(I 積分時間)を変化させたときの応答
| 大きくすると | 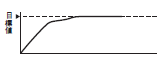 | 目標値になるまでの時間が長くなります。 整定時間がかかりますがハンチングやオーバーシュート、アンダーシュートが 小さくなります。 |
| 小さくすると | 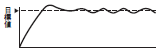 | オーバーシュート・アンダーシュートが起こります。 ハンチングが生じます。 早く立ち上がります。 |
D(微分時間)を変化させたときの応答
| 大きくすると | 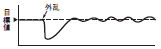 | アンダー整定時間が小さくなりますが自分自身の変化に 細かいハンチングを生じます。 |
| 小さくすると | 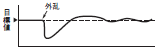 | アンダーが大きくなり、目標値にもどるまで時間がかかります。 |
●セルフチューニング(ST)
運転開始時と目標値変更時にステップ応答法によりPID定数を求めます。
一度PID定数を求めたあとは、目標値が変更されない限り次回の運転開始時にセルフチューニングは実行されません。
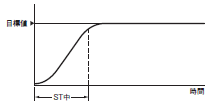
形式とチューニング方式一覧表
| 形式 | チューニング方式 |
| 形E5□C | AT、 ST |
| 形E5□N * | AT、 ST |
| 形E5□R | AT |
| 形E5CS-U/形E5CSV | AT、 ST |
| 形E5CB | AT |
| 形EJ1 | AT |
| 形E5ZN | AT |
| 形C200H-TC | AT |
| 形C200H-TV | AT |
| 形C200H-PID | AT |
ST:セルフチューニング
AT:オートチューニング
*形E5ZNは含みません。
●制御出力
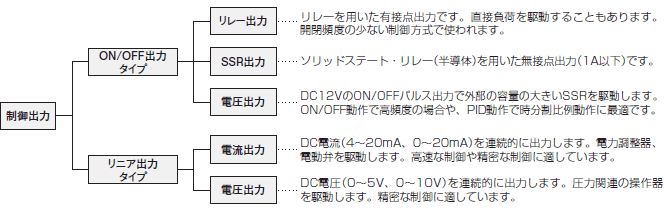
警報に関する用語
●警報出力
温度調節器により警報の信号を警報出力に出力するタイプと、出力先を補助出力や制御出力に設定で割り付けるタイプがあります。
●警報動作
警報は現在値、警報値、目標値を比較し、警報種別により指定された動作モードに従い信号を出力します。おもな動作モードには、偏差警報、絶対値警報、待機シーケンス付警報、ヒータ断線警報、SSR故障警報、ループ断線警報、およびそれらを組み合わせたものがあります。
●偏差警報
警報設定値の指定方法で、温度調節器の目標値(SP)を中心とし、その値からのへだたり(偏差)の値を警報設定値とします。
温度に関する警報で特に指定しない場合は、偏差警報を指します。
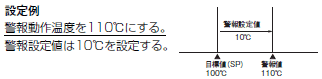
●絶対値警報
警報設定値の指定方法で、温度調節器の目標値(SP)にかかわりなく、警報動作を行う温度を警報設定値とします。
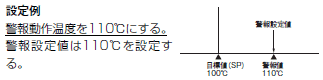
●待機シーケンス付警報
温度制御開始時など、温度がはじめから警報動作の指定範囲内に含まれるときがあります。そのため、いきなり警報が出力されてしまうことになります。これを避けるために、待機シーケンス付機能を指定できます。温度が電源投入時、または制御開始後、一度は警報範囲外、つまり警報が出力されない温度にあったことを確認して、その後に警報範囲内に入ったときに警報が出力されます。
待機シーケンス付上下限警報設定時の警報出力例
温度が上がる場合
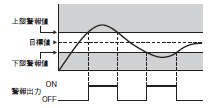
温度が下がる場合
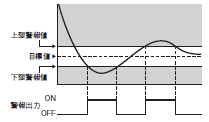
●SSR故障警報
SSRは構造的に短絡モードで故障することが多く、短絡故障するとヒータの温度が上昇し続け危険な状態になる場合があります。SSRの短絡故障を検出し警報を出力するのがSSR故障警報です。電流検出器(CT)を用いてヒータ電流を検出し、SSRを駆動する温度調節器の出力がOFFしているにもかかわらず電流が流れ続けている場合、SSR故障警報を出力します。
●ヒータ断線警報
ヒータが切れたことに気付かず装置の運転を続けると、製品が不良になったり、最悪の場合、装置が壊れてしまう場合があります。ヒータの断線やヒータケーブルの断線を検出するのがヒータ断線警報です。電流検出器(CT)を用いてヒータの電流を検出し、ヒータを駆動する温度調節器の出力がONしているにもかかわらずヒータに電流が流れない場合、ヒータ断線警報を出力します。電流検出器(CT)を2個接続できるタイプの温度調節器を用いると三相ヒータのヒータ断線を検出することができます。
*温度調節器の出力が電流出力タイプの場合、ヒータ断線警報は使用できません。
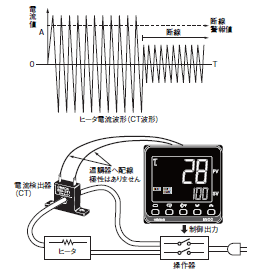
●警報ラッチ
警報出力がいったんONになると、警報ラッチの解除操作をするまで温度にかかわりなく警報をONし続ける機能です。
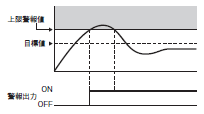
●LBA(ループ断線警報)
制御しているにもかかわらず、偏差が一定以上あり偏差が減少する方向に入力が変化しないとき、制御ループのどこかに異常があるものとして警報出力する機能です。ヒータ交換後にセンサを付け忘れて運転を開始した場合やセンサ抜けの検出手段として利用できます。
温度入力に関する用語
●冷接点補償
熱電対は、温接点部と反対側の冷接点部の温度差に応じた電圧(熱起電力)を生じます。したがって、熱電対は絶対温度ではなく相対温度を出力します。温度調節器は熱電対の出力する相対温度から絶対温度を求めるため、冷接点部の温度を検出しその温度に相当する熱起電力を熱電対の熱起電力に加算することにより冷接点部の温度の影響を補償(キャンセル)します。この電圧加算により温接点部の絶対温度を求める方法を冷接点補償と呼びます。
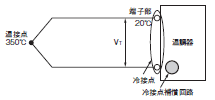
上図において、温度調節器の入力端子部にて測定される熱起電力VTは① VT=V(350,20)となります。
ここでV(A,B)は温接点A℃、冷接点B℃としたときの熱起電力を表します。
また、熱電対の基本的な性質である「中間温度の法則」より、②V(A,B)=V(A,C)-V(B、C)が成立します。
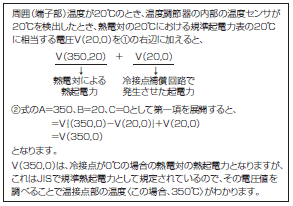
●補償導線
熱電対温度センサのケーブルが温度調節器に届かない場合、銅線でセンサと温度調節器の間を延長すると大きな温度誤差を生じます。熱電対温度センサのケーブルを延長する場合は補償導線を用いる必要があります。
補償導線は常温付近で熱電対とほぼ同等の熱起電力を発生するケーブルで、使用する熱電対に合った補償導線を使わなければなりません。
補償導線は熱電対のケーブルに比べ一般的に安価で、各熱電対に合った補償導線が市販されています。
補償導線を用いた例
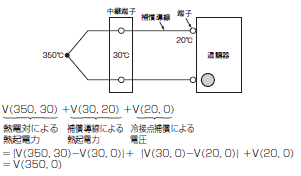
白金測温抵抗体またはサーミスタの温度センサのケーブルを延長する場合、補償導線を用いると逆に大きな温度誤差を生じます。
十分導線抵抗が小さいケーブルを用いて延長してください。
●入力補正
温度センサの測定温度に入力補正値を加減算した値を温度調節器の現在温度に表示します。温度センサの測定点と実際に温度を測りたい点が異なり、あらかじめ温度差がわかっている場合に温度調節器の表示を補正する場合などに用います。
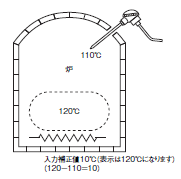
出力に関する用語
●逆動作(加熱)
目標値より温度が低い場合、操作量を増やすように動作します。加熱制御は逆動作です。
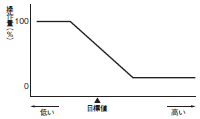
●正動作(冷却)
目標値より温度が高い場合、操作量を増やすように動作します。冷却制御は正動作です。
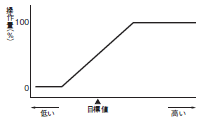
●加熱冷却制御
制御対象の温度制御が加熱のみでは制御が難しい場合、冷却と合わせ制御を行うことがあります。1台の温度調節器から加熱用制御出力、冷却用制御出力をだし制御を行います。
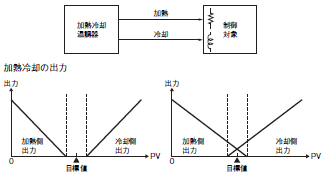
●操作量リミッタ
「操作量リミット上限値」および「操作量リミット下限値」で出力する操作量の上限値と下限値を設定します。温度調節器が計算した操作量が、操作量リミッタの範囲外になったとき、実際の出力は上限値または下限値に従います。
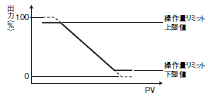
加熱冷却制御では、冷却側の操作量を便宜上負の値として扱っているので、一般に次の図のように、上限値は加熱側(正の値)、下限値は冷却側(負の値)に設定します。
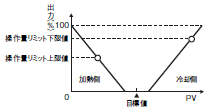
●変化率リミット
「操作量変化率リミット値」で1秒あたりの操作量の変化量を設定します。温度調節器が計算した操作量が大きく変化したとき、実際の出力は操作量変化率リミッタの設定内容に従って徐々に計算値に近づきます。
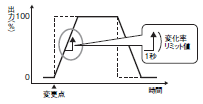
●デッドバンド
加熱冷却制御の場合のオーバーラップバンド、デッドバンドを設定します。この値をマイナス値にするとオーバーラップバンド、プラス値にするとデッドバンドとなります。
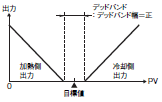
加熱側出力と冷却側出力が同時に出力されることはありません。
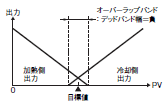
目標値付近で加熱側出力と冷却側出力が同時に出力されます。
●冷却係数
加熱冷却制御が可能で加熱側と冷却側それぞれ個別にPID定数をもたない温度調節器は、制御対象の加熱特性と冷却特性が大きく異なり同一のPID定数で良好な制御性が得られない場合があります。その場合は、冷却係数によって冷却側の比例帯(冷却側P)を調整して、加熱側と冷却側の制御バランスをとってください。加熱側および冷却側のPは次の式で求められます。
加熱側P=P
冷却側P=加熱側P×冷却係数
冷却側Pは加熱側Pに係数をかけて、加熱側とは異なる特性で制御を行います。
冷却側P=加熱側P×0.8
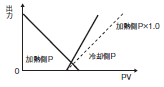
冷却側P=加熱側P×1.5
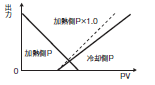
●加熱冷却PID制御
加熱側PIDと冷却側PIDをそれぞれ独立して設定できる温度
調節器では、「加熱冷却チューニング方式」により冷却側の制御特性に応じた調整法を選択しAT(オートチューニング)を実行することによりそれぞれのPID定数が自動設定されます。
| 設定データ | 設定 |
| 加熱冷却チューニング方式 | 加熱と共通 |
| リニア | |
| 空冷 | |
| 水冷 |
リニア
線形(リニア)な冷却特性を持つアプリケーションに対応した制御を行います。
空冷/水冷
非線形な冷却特性を持つアプリケーション(プラスチック成形機など)に対応した制御を行います。
即応性がよく、安定した応答特性が得られます。
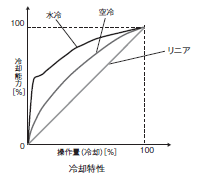
●位置比例制御
オンオフサーボ形とも呼ばれています。
温度制御用にコントロールモータ、またはモジュトロールモータのついたバルブを使用する場合(オープン・クローズ制御)、ポテンションメータでバルブの開度を読み取り、開く(オープン)、閉じる(クローズ)の信号を出し、操作量を伝え制御します。温度調節器の出力はオープン用、クローズ用の2つの信号がでます。
なおフローティング制御(ポテンションメータでバルブ開度をフィードバックしない:ポテンションメータがなくても制御可能)も選択できます。
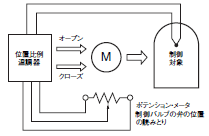
●伝送出力
現在値、目標値などを通信以外の手段で記録計や他の温度調節器、PLCなどに伝えたい場合があります。伝送出力は温度調節器の現在温度、目標値などのうちどれか1つの値を4~20mAの電流値に変換しに出力する機能です。受け側も4~20mAの電流入力に対応していなければなりません。
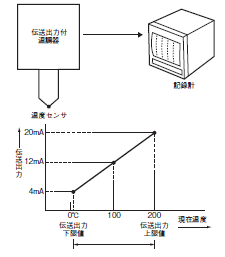
設定に関する用語
●目標値設定リミット
目標値を設定できる範囲は温度センサの種別で決まるため、かなり大きな値が設定できます。実際に使用する温度より高い温度を設定すると装置が故障したりする場合は目標値リミットで設定できる温度範囲を制限することができます。
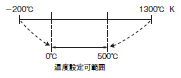
●マルチSP
複数の目標値を設定しておき、フロントキーの操作やイベント入力で切り替える機能です。
●バンク
複数の目標値、PID定数、警報値を有する温度調節器(調節計)はバンクという括りでこれらのパラメータをグループ化し保存します。制御時にはバンクを切り替えることにより一括してバンクに登録されたパラメータを変更することができます。
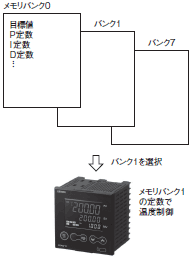
●SPランプ
決まった昇温速度で温度を上げたい場合、または決まった時間で目標温度まで温度を上げたい場合などに使う機能です。
SPランプ機能を有効にすると目標値に到達するまで下図のように目標値が設定されその目標値に対し制御を行います。
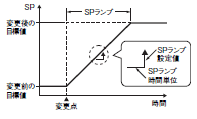
●リモートSP
外部からのアナログ信号(4~20mA)で目標値を設定、変更する機能です。リモートSP機能を有効にすると、リモートSPを目標値として制御します。
●イベント入力
ON/OFF信号を温度調節器に入力する機能で、マルチSPの切り替え、RUN/STOPなどの機能を割り付け、外部から温度調節器を操作することができます。
●入力デジタルフィルタ
センサ入力信号に対し外部のノイズが大きく制御や計測が安定しない場合に使用します。制御に用いられる現在値は入力デジタルフィルタ通過後の値です。入力デジタルフィルタの設定値はデジタルフィルタの時定数で、時定数とフィルタ通過後の現在値(PV)の関係は下図のとおりです。
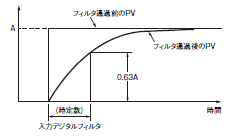
-
 PDF版をダウンロード 6930KB
PDF版をダウンロード 6930KB




 マイカタログに追加
マイカタログに追加 Facebook
Facebook