 使用上の注意事項
使用上の注意事項
-
 コントロール
コントロール
-
 温度調節器(デジタル調節計)
温度調節器(デジタル調節計)
- タイマ/タイムスイッチ
-
 カウンタ
カウンタ
-
 デジタルパネルメータ
デジタルパネルメータ
-
 信号変換器
信号変換器
-
 通報装置
通報装置
-
タイマ/タイムスイッチ 共通の注意事項
タイマ/タイムスイッチは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置です。ここではタイマ/タイムスイッチの共通の注意事項を説明します。
| 共通の注意事項 |
●各商品個別の注意事項は、各商品ごとの「正しくお使いください」をご覧ください。
 注意
注意
下記の製品は、リチウム電池(防爆タイプ)を使用しています。

電池内蔵タイプ:形H5S、形H5F、形H4KV、形H5L
リチウム電池を内蔵しており、稀に発火、破裂の恐れがあります。分解、加圧変形、100℃以上の加熱、焼却はしないでください。
安全上の要点
●使用環境について
- 使用周囲温度や使用周囲湿度については、各商品ごとに記載された定格範囲内でご使用ください。
- 保存は、各商品ごとに記載された定格範囲内としてください。また、-10℃以下で保存後使用する場合は、常温に3時間以上放置してから通電してください。
- 冠水・被油については、各商品ごとに記載された性能に基づきご使用ください。
- 振動・衝撃の加わる場所では、長期ご使用によりストレスで破損の原因となりますのでご使用は避けてください。
マグネットコンタクタは負荷開閉時に1,000 ~2,000m/s2の衝撃が発生しますので、DINレールに取りつける場合など、タイマ本体に振動、衝撃が加わらないように離してお取りつけください。また、防震用ゴムをご使用ください。 - 塵埃の多いところ、腐食性ガスの発生する場所、直射日光のあたる場所での使用は避けてください。
- タイマ本体の外装は有機溶剤(シンナー・ベンジンなど)、強アルカリ、強酸性物質に浸されるためご注意ください。
- ノイズ発生源、ノイズがのった強電線から入力信号源の機器、入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
- 多量の静電気が発生する環境(成形材料、粉・流体材料のパイプ搬送の場合など)でご使用の場合は静電気発生源をタイマ本体より離してください。
- 外装ケースは取りはずさないでください。
- 急激な温度変化、湿度の高い場所では、回路内に結露が発生し、誤動作や素子が破損する場合がありますのでご使用環境をご確認ください。
- 密着取りつけをすると内部部品の寿命が短くなる恐れがあります。
- 樹脂製品、ゴム製品(ゴムパッキンなど)は使用環境(腐食性ガス下、紫外線下、高温での使用など)により劣化し、収縮および硬化するため、定期的な点検および交換をおすすめします。
- 下水道関連やゴミ焼却など、硫化ガス発生の可能性がある場所では、正常動作ができなくなる場合があります。当社タイマ類、また一般的な制御機器では硫化ガス雰囲気での使用を保証した商品はございませんので、硫化ガスが入らないように密閉してご使用ください。密閉できない場合、一部のタイマで硫化ガス耐性を強化した特殊品を用意しております。詳細は、当社営業担当者までご相談ください。
●電源について
- 定格以外の電圧を印加しますと、内部素子が破壊する恐れがあります。
- 作業者がすぐ電源OFF できるよう、スイッチまたはサーキットブレーカを設置し、適切に表示してください。
- 電源電圧の変動範囲は、許容範囲内としてください。
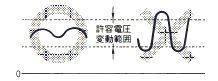
- 電源電圧入力において、AC 入力タイプは商用電源をご使用ください。
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、タイマの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をタイマの電源として使用しないでください。 - 交流2線式の近接センサにてタイマの電源をON/OFFする場合、以下掲載のタイマでは直接ON/OFFすることができません。
交流2線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は以下の対策を実施ください。(タイマの電源回路が半波整流方式となっており、近接センサへは交流半波しか供給されず、動作が不安定になる可能性があります。)
〈対象形式〉
形H3Y、形H3YN、形H3RN、形H3CA-8、形RD2P、形H3CR-A、-A8、-AP、-AS、-F、-A8E(-A8EはAC100-240Vのみ)
〈対策〉
リレーを介して、リレー接点にて電源ON/OFFを行ってください。
接続後は動作安定性の確認を行ってください。
- 電源側には、「電気設備に関わる技術水準」「労働安全衛生規則」などの関連法規に従って、保護装置(漏電遮断器、配線用遮断器、ヒューズなど)を設定してください。
●正しい入力信号処理について
入力の接続線は、電源線・動力線・高圧線との同一電線管配線などするとノイズ誤動作の原因となるのでこれら強電線
から離して独立の配線をしてください。また、シールド線、または金属電線管を使用して短く配線してください。
●リレータイプの場合
- 絶縁不良、接点の溶着、接触不良など、規定の性能を損なうばかりでなく、リレー自体の破損・焼損の原因となります。開閉容量(接点電圧・接点電流)などの接点定格値を超える負荷に対しては絶対に使用しないでください。
- 性能の劣化した状態で引き続きご使用されますと最終的には、回路間の絶縁破壊やリレー自体の焼損などの原因となります。内蔵リレーの寿命は開閉条件により大きく異なります。使用にあたっては必ず実使用条件にて実機確認を行い、性能上問題のない開閉回数内にてご使用ください。
- 電気的寿命は、負荷の種類・開閉ひん度・周囲の環境により異なりますので、ご使用にあたっては次のような点にご注意ください。交流負荷で開閉時の位相が同期しているまたは、DC負荷の開閉では、接点転移により接点の引っ掛かりや接触不安定となることがありますので、確認と共にサージ吸収用素子を検討ください。高ひん度での開閉の場合、発生したアークによる発熱で接点の溶け、また、金属腐食の原因となりますのでアーク吸収用素子の取りつけ・開閉ひん度を下げる・湿度を下げるなどご検討ください。
- 負荷の種類によって突入電流が異なり接点の開閉ひん度・使用回数などにも影響します。定格電流と共に突入電流を確認して余裕をもった回路設計を行ってください。
| 抵抗負荷 | ソレノイド負荷 | モータ負荷 | 白熱電球負荷 |
| 定格電流の1倍 | 定格電流の10~20倍 | 定格電流の5~10倍 | 定格電流の10~20倍 |
| ナトリウム灯負荷 | コンデンサ負荷 | トランス負荷 | 水銀灯負荷 |
| 定格電流の1~3倍 | 定格電流の20~40倍 | 定格電流の5~15倍 | 定格電流の1~3倍 |
- 開閉に伴うアークやリレーの発熱などにより、発火または爆発を引き起こす恐れがあります。引火性ガス・爆発性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
- 接点不良の原因となります。硫化ガス・塩素ガス・シリコンガスなどの雰囲気では使用しないでください。
- 直流電圧の負荷を開閉される場合、交流電圧の場合と比較して開閉可能な容量が低下します。
●無接点出力タイプの場合
- 出力素子の破壊によりショート故障またはオープン故障の原因となります。定格出力電流を超える負荷に対しては、絶対に使用しないでください。
- 逆起電圧により出力素子が破壊され、ショート故障またはオープン故障の原因となります。直流誘導負荷に使用される場合、必ず逆起電圧対策のダイオードを接続してください。
●その他
- ご希望通りの製品であるかお確めの上、ご使用ください。
- 端子接続は、誤配線のないように注意してください。
- キープリレーを内蔵しているタイマ(形H3CR-Hなど)においては輸送・取扱い中の落下などの衝撃により出力接点が反転、中立状態になる場合があります。ご使用前にテスタなどで出力状態を確認してください。
- 高温中に長時間、タイムアップの状態(内部リレーがONした状態)で放置されますと、内部部品(電解コンデンサなど)の劣化を早める恐れがあります。
そのためリレーと組み合わせて使用するようにし、長時間(たとえば1ヵ月以上)のタイムアップ放置は避けてください。
参考例(下記のようにしてお使いください。)
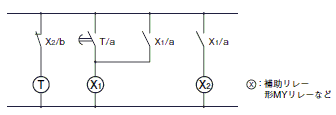
- 製品の取りつけ電気工事は、必ず有資格者(電気工事士)が行ってください。
使用上の注意
●動作時間のセット
- 動作時間セットの場合、つまみは目盛の範囲以上に回さないようにしてください。より正確な時限が必要な場合はご使用前に動作時間を測定しツマミで調整してください。
- アナログタイマの動作時間のばらつき値は、最大目盛時間に対する%で表しているため、セット時間を変えてもばらつきの絶対値は変わりません。従って、できるだけ最大目盛の近くで使用できるよう時間仕様を選んでください。
- アナログタイマを時限中に設定変更をした場合は下記の動作になります。
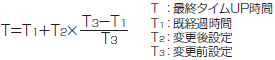
●制御出力
- 制御出力接点の負荷電流は、定格および負荷回路の接続に示す適用負荷以下でご使用ください。定格以上の値で使用すると、接点寿命が著しく短くなるためご注意ください。
- 微小負荷開閉時には、各商品ごとに記載された最小適用負荷をご確認ください。
- 制御出力用接点の寿命は、開閉条件により大きく異なります。使用にあたっては、必ず実使用条件にて実機確認を行い、性能上問題のない開閉回数内にてご使用ください。性能の劣化した状態で引き続き使用されますと、最終的には、回路間の絶縁不良や制御出力用リレー自体の焼損の原因となります。
- 次のような接続はタイマ内部の異極接点間でレアショートが発生する可能性がありますので行わないでください。
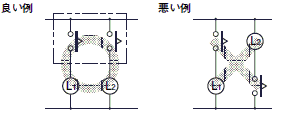
- 微小負荷開閉時には、各商品ごとに記載された最小適用負荷をご確認ください。
●電源について
- 徐々に電圧を印加しますと電源リセットされなかったりタイムアップすることがあります。電源電圧はスイッチ、リレーなどの接点を介して一気に印加してください。
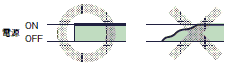
- 電源投入時に短時間ですが突入電流(タイマ/タイムスイッチ 技術解説の「参考資料」参照)が流れ電源の容量によってはタイマが起動しないことがありますので、十分な容量の電源をご使用ください。
- 電源の接続は、AC電源でご使用の場合は、極性に関係なく指定の2極端子に接続できますが、DC電源の場合は極性にご注意ください。
- また、定格電圧と異なる電圧を印加した場合、誤配線やDC仕様で極性が逆になった場合、誤動作、異常発熱、焼損の原因となりますのでご注意ください。
- DC電源の場合、規定のリップル率としてください。
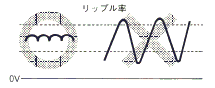
代表的な簡易電源とリップル率は下記のとおりです。
| 整流方式 | リップル率 |
| 単相全波 | 約48% |
| 三相全波 | 約4% |
| 三相半波 | 約17% |
注. 各タイマのリップル率をご参照ください。
- 電源端子間への外来インパルス電圧については、日本電気学会制定のインパルス電圧電流試験一般(JEC-210)に準じ、±(1.2×50)μsの標準波形で確認しています。
また、電源重畳サージやノイズが加わった場合、内部素子の破壊や誤動作の原因となりますので、回路の波形を確認いただくと共にサージ吸収用素子のご使用をおすすめします。発生しているサージ・ノイズにより素子の効果が異なりますので、実機でご確認ください。 - 電源OFF 時に残留電圧・誘導電圧が加わらないようにしてください。
●設定
キースイッチによる設定の際、爪や先端の鋭敏な工具を使用しないでください。爪や先端の鋭敏な工具などを用いますと、キーが破損する恐れがあります。
また、タイムスイッチにおいては、通電中に各時刻や各種設定を変更する場合は、必ず負荷側の電源を切るか、出力「入」「切」スイッチを「切」にして、安全を十分確保した上で行ってください。
●その他
- 制御盤に組み込まれた状態で、電気回路と非充電金属部間の耐電圧試験、インパルス電圧試験・絶縁抵抗測定などをする場合、制御盤の一部の機械、部品に耐圧、絶縁不良が生じた場合にタイマ内部回路の劣化破損の防止のため、
①タイマを回路から切り離してください。(ソケットをタイマから引き抜く、配線をはずすなど)または、
②端子部の全端子を短絡してください。 - 無接点出力形の機器(たとえば近接スイッチ・光電スイッチやソリッドステート・リレーなど)をもってタイマを直接操作される場合には、無接点機器の漏れ電流によりタイマが誤動作する場合がありますので、使用前に十分ご確認ください。
- 電池交換時は配線をはずしてください。高電圧が印加された個所に触れて感電する恐れがあります。
- 誘導負荷を開閉する場合、タイマの誤動作、破壊を防止するためにサージ吸収素子をつけてください。
サージ吸収素子例として、直流回路ではダイオード、交流回路ではサージアブソーバなどがあります。
サージキラーの代表例
| 回路例 | 適用 | 特長、その他 | 素子の選び方の目安 | ||
| 分類 | AC | DC | |||
| CR方式 | 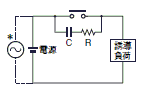 | * △ | ○ | *AC電圧で使用する場合 負荷のインピーダンスがC、 Rのインピーダンスより十分 小さいこと。 接点が開路のとき、C、Rを 通して、誘導負荷に電流が 流れます。 | C、Rの目安としては C:接点電流1Aに対し0.5~1(μF) R:接点電圧1Vに対し0.5~1(Ω) です。ただし負荷の性質や特性の バラツキなどにより異なります。 Cは接点開離時の放電抑制効果を 受けもち、Rは次回投入時の電流 制限の役割ということを考慮し、 実験にてご確認ください。 Cの耐電圧は一般に200~300Vの ものを使用してください。 AC回路の場合はAC用コンデンサ (極性なし)をご使用ください。 ただし直流高電圧で接点間のアー クの遮断能力が問題となる場合に、 負荷間より接点間にCRを接続した 方が効果的な場合がありますので 実機にてご確認ください。 |
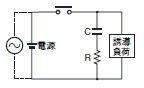 | ○ | ○ | 負荷がリレー、ソレノイドな どの場合は復帰時間が 遅れます。 | ||
| ダイオード方式 | 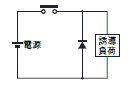 | × | ○ | 誘導負荷に貯えられた電磁 エネルギーを並列ダイオー ドによって、電流の形で誘 導負荷へ流し、誘導負荷 の抵抗分でジュール熱とし て消費させます。 この方式はCR方式よりも さらに復帰時間が遅れます。 | ダイオードは逆耐電圧が回路電圧 の10 倍以上のもので順方向電流は 負荷電流以上のものをご使用くださ い。 電子回路では回路電圧がそれほど 高くない場合、電源電圧の2~3倍 程度の逆耐電圧のものでも使用 可能です。 |
ダイオード + ツェナー ダイオード方式 | 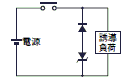 | × | ○ | ダイオード方式では復帰 時間が遅れすぎる場合に 使用すると効果があります。 | ツェナーダイオードのツェナー 電圧は、電源電圧程度のものを 使用します。 |
| バリスタ方式 | 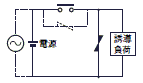 | ○ | ○ | バリスタの定電圧特性を 利用して、接点間にあまり 高い電圧が加わらないよう にする方式です。 この方法も復帰時間が多少 遅れます。 電源電圧が24~48V時は 負荷間に、100V~200V時 は接点間のそれぞれに 接続すると効果的です。 | バリスタのカット電圧Vcは下記の 条件内になるように選びます。 交流では√2倍することが必要です。 Vc>(電源電圧×1.5) ただし、Vcを高く設定しすぎると 高電圧へのカットが働かなくなる ため効果が弱くなります。 |
なお、次のようなサージキラーの使い方は避けてください。
 | しゃ断時のアーク消弧には非常に 効果がありますが、接点の開路時 C にエネルギーが蓄えられている ため、接点の投入時に短絡電流が 流れるので、接点が溶着しやすい。 |  | しゃ断時のアーク消弧には非常に 効果がありますが、接点の投入時に C への異常な充電電流が流れる ので接点が溶着しやすい。 |
通常、直流誘導負荷は、抵抗負荷に比べ開閉が困難とされていますが、適切なサージキラーを用いると抵抗負荷と同程度まで性能が向上します。
- タイムアップ後、すぐタイマを復帰させる場合には、復帰タイミングが十分とれるよう回路構成にご注意ください。復帰タイミングがとれないとシーケンスに異常が発生することがあります。
- デジタルタイマは、常時読込方式を採用しています。動作中に設定値を変更する場合、現在計測値をまたぐような変更をするとその時点で出力状態が変化します。
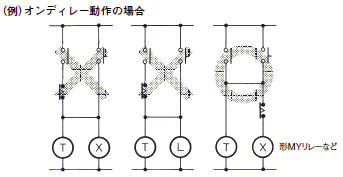
取りつけについて
●表面取りつけ
取りつけ方向は特に制限はありませんが、水平方向で確実に取りつけてください。
〈形P2CFソケットを使用する場合〉
(1)タイマを縦に並べてご使用の場合は、フックの可動部分を考慮して、ソケットの上、下に20mmほど余裕をもたせてください。
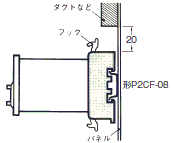
〈DINレールに取りつける場合(形H3CA-FA)〉
(1)(A) 部をレールの一端にひっかけ(B)方向に押し込んでください。
(2)取りはずす場合は部にドライバを差し込み、引きはずしてください。
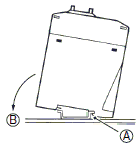
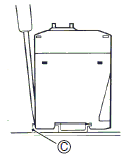
〈形PLを使用する場合〉
(1)ソケットをパネルの表面から差し込んで取りつけ、L用フックをソケットと共にねじ止めしてください。
(2)本体をソケットに差し込み、フックの先端を指先で押さえてください。
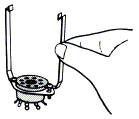
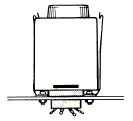
〈付属取りつけ金具につける場合(形H5L)〉
(1)付属取りつけ金具に製品を製品を取りつけてください。
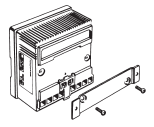
(2)付属取りつけ金具の両端の穴を利用し取付け面に固定してください。
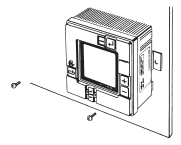
〈ねじを使用して取りつける場合(形H5F-FA/FB)〉
(1)付属のM4タッピングねじにて、取りつけしてください。
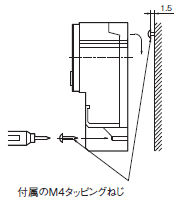
〈DINレール取りつけ用ベースを使用してDINレールに取りつける場合(形H5S-FA/FB)〉
(1)付属のDINレール取りつけ用ベースに製品を取りつけてください。
(2)付属のDIN レール取りつけ用ベースの取りつけ部にてDINレールに固定してください。
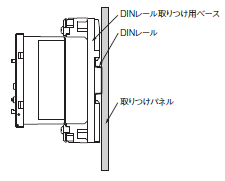
〈形PF085A、形P2Bを使用する場合①〉
(1)ソケットをパネル表面へねじ止めし、F 用フックをソケットへ差し込んでください。
(2)本体をソケットに差し込み、フックの先端を指先で押さえてください。
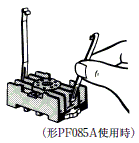
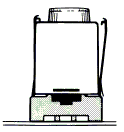
〈形PF085Aを使用する場合②〉
(1)ソケットをパネル表面へねじ止めし、F 用フックをソケットへ差し込んでください。
(2)本体をソケットに差し込み、フックの先端を指先で押さえてください。
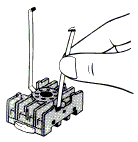
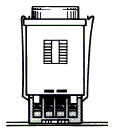
〈形8PFAソケットを使用している場合〉
・形8PFA ソケットにベースアダプタ形Y92F-42を取りつけます。
・上部よりソケットタイプの48×48mmタイマをはめ込みます。 このアダプタはフックを使って固定するものです。配線を変換するものではありませ
ん。
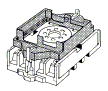
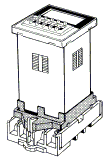
●埋込み取りつけ
・パネルの板厚は1.0~3.2mmとしてください。(商品により多少異なりますので、詳細は商品カタログをご参照ください。)
・形Y92F-30埋込み取りつけ用アダプタを使用する場合本体をパネル前面から角穴へ入れ、裏面からアダプタを挿入し、パネル面との隙間が少なくなるよう押し込んでください。さらにねじで固定
してください。
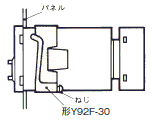
・本体をタテ方向に連続取りつけをする場合、形Y92F-30の成形ばね部が左右になるように配置します。
・本体をヨコ方向に連続取りつけをする場合、形Y92F-30 の成形ばね部が上下になるような配置にします。
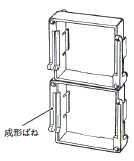
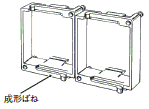
・形US-08 を使用する場合は、配線には仕上がり外径φ10.5mm以下の多芯コードまたは、外径φ3mm以下の絶縁電線(より線)をご使用ください。
・形Y92F-40、形Y92F-70、形Y92F-71、形Y92F-73、形Y92F-74の埋込み取りつけ用アダプタをご使用の場合は、本体をパネル角穴へ押し込むだけでOKです。パネル塗装が厚くて、フックがカチッと挿入できないときは、タイマをパネルに挿入後、フックを裏面より左右に十分広げてください。
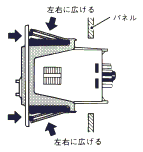
図は形Y92F-70の例です。
取りはずしについて
●表面取りつけ(形P2CFの場合)
親指でフックをはずしてください。
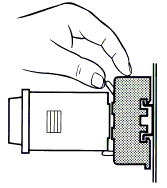
●表面取りつけ(形PF085Aの場合)
人差し指でフックを押さえながら、親指ではずしてください。
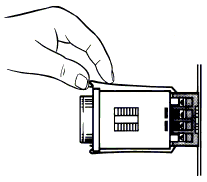
●埋込み取りつけ
・アダプタのねじをゆるめフックを広げ、アダプタをはずしてください。
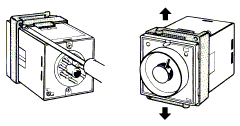
・形Y92F-40、形Y92F-70、形Y92F-71、形Y92F-73、形Y92F-74を使用した場合、両手の親指、人差し指でフックを内側へ押さえながら前方向にタイマ本体を押し出してください。
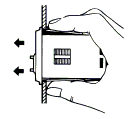
選定上の確認項目
(1)電源電圧は。
(2)消費電力は。
(3)動作方式、復帰方式は。
(4)接点構成、接点容量は。
(5)動作時間範囲は。
(6)復帰時間は。
(7)寿命(機械的・電気的)は。
(8)温度、湿度、ほこり、振動、衝撃などタイマの使用環境は。
(9)タイマ周辺機器、許容電圧変動範囲などタイマの周辺電源環境は。
(10)タイマの使用動作ひん度は。
(11)時間セットかタイミングセットか。セットひん度は。
(12)時間精度は。
(13)取りつけ方法、取りつけ方向は。
(14)大きさの制限は。
-
 PDF版をダウンロード 1616KB
PDF版をダウンロード 1616KB




 マイカタログに追加
マイカタログに追加 Facebook
Facebook