一般リレー トラブルシューティング
一般リレーは、電磁継電器のことで、電気信号を受けて機械的な動きに変える電磁石と電機を開閉するスイッチで構成されます。ここでは一般リレーのトラブルシューティングを示します。
故障事例
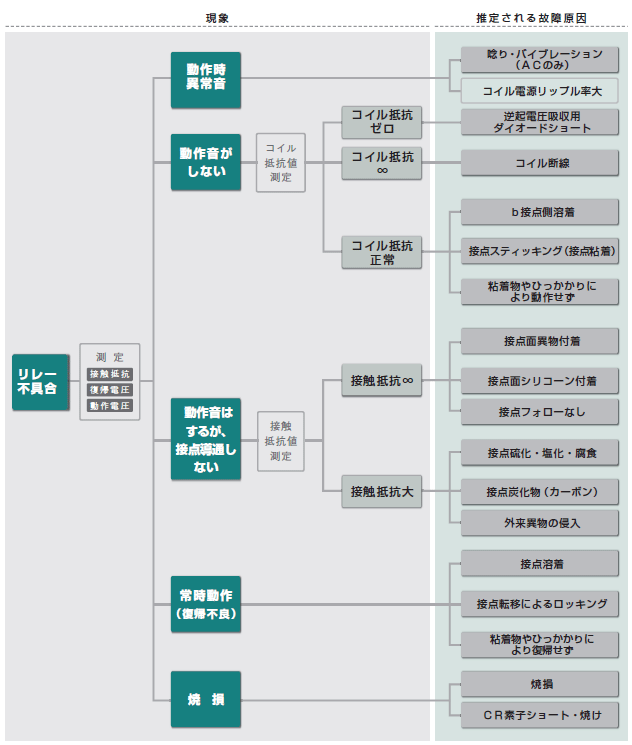
注1.お客様にて打診される場合は、ケースを開けての打診はご遠慮くださいますようお願いいたします。
注2.原因推定、対策等の詳細は、「リレーの不具合 原因と対策 The 解決 テクニカルガイド」(カタログ番号:SGFR-330)をご覧ください。
故障と原因推定
リレーを使用する装置の場合、リレーに関する色々なトラブルが発生することがあります。
そのとき、FTA(Fault Tree Analysis)的考え方から、その原因を追求しなければなりません。下表では、リレーに関する故障モードを取りあげ、故障原因の推定を行います。
リレーの外部から見た現象
| 故障 | チェック内容 | 原因推定 |
| リレーが働かない | ① 入力電圧がリレーに届いているか | ・ブレーカーやヒューズがおちている ・配線の誤り、漏れ ・ねじ端子の締め付けが不十分 |
| ② 入力電圧に見合った仕様の リレーが使われているか | ・AC100V電圧ラインにAC200V仕様のリレーを使用 | |
| ③ 入力電圧の電圧降下はないか | ・供給電源が容量不足 ・長距離配線 | |
| ④ リレーが破損していないか | ・コイルが断線 ・落下、衝撃による機械的破損 | |
| ⑤ 出力回路に異常がないか | ・出力側電源 ・負荷の不良 ・配線ミス ・接続不良 | |
| ⑥ 接触不良していないか | ・接点の異常 ・寿命による接点消耗 ・機械的破損 | |
| リレーが復帰しない | ① 印加電圧が完全に切れているか | ・保護回路(サージアブソーバ)のリーク電流 ・迂回路による電圧印加 ・残電圧が残る半導体制御回路 |
| ② リレーの異常 | ・接点溶着 ・絶縁劣化 ・メカ的破損 ・誘導電圧(長距離配線) | |
| リレーが誤動作する 表示灯が異常点灯する | ① リレーの入力端子に異常電圧が 加わっていないか | ・誘導電圧(長距離配線) ・誘導電圧による迂回路 (ラッチングリレーのキープはずれ) |
| ② 過大な振動、衝撃が加ってないか | ・劣悪な使用環境 | |
| 焼損 | ① コイル部からの焼損か | ・コイル仕様の選定誤り ・定格以上の電圧が印加 ・AC仕様で電磁石の不完全動作(鉄片の吸着が不十分) |
| ② 接点部からの焼損か | ・接点の定格以上の電流 ・許容以上の突入電流 ・短絡電流 ・外部との接続不良 (ソケットなどとの接触不良によって異常発熱) |
リレーの内部から見た現象
| 故障 | チェック内容 | 原因推定 |
| 接点溶着 | ① 大きな電流が流れなかったか | ・ランプ負荷などのラッシュ電流 ・負荷の短絡電流 |
| ② 接点部の異常振動がなかったか | ・外部からの振動、衝撃 ・ACリレーのうなり ・電圧の低下による不完全動作による接点のチャタリング (モータを動作させた瞬間、電圧が低下する場合がある) | |
| ③ 開閉頻度が多すぎないか | ―― | |
| ④ リレーの寿命がきてないか | ||
| 接触不良 | ① 接点表面に異物が付着していないか | ・シリコンやカーボンその他異物の付着 |
| ② 接点表面が腐食していないか | ・SO2、H2Sによる接点の硫化 | |
| ③ 機械的接触不良になっていないか | ・端子のずれ、接点のずれ、接点フォロー | |
| ④ 接点が消耗してないか | ・リレーの寿命 | |
| うなり | ① 印加電圧が不足していないか | ・リレーのコイル仕様の誤り ・印加電圧のリップル ・入力電圧の緩慢な上昇 |
| ② リレータイプの誤りがないか | ・ACラインにDC仕様を使用 | |
| ③ 電磁石の動作不完全がないか | ・可動片と鉄心間に異物の混入 | |
| 接点の異常消耗 | ① リレー選定はあっているか | ・電圧、電流、突入電流の定格選定ミス |
| ② 接続負荷への配慮はなされているか | ・モータ負荷、ソレノイド負荷、ランプ負荷などの突入電流 |
注.原因推定、対策等の詳細は、「リレーの不具合 原因と対策 The 解決 テクニカルガイド」(カタログ番号:SGFR-330)をご覧ください。
メンテナンスの考え方
メンテナンスの方法には、大別して故障が起こってから点検や取替えを行う事後のメンテナンスと、故障が起こらないうちに点検やメンテナンスを行う予防メンテナンスの2通りがあります。
このうち予防メンテナンスでは、いつ点検や取替えを行うか、またその時期をどのようにして知るかということや、どのように定めるかが重要な課題となります。
リレーのメンテナンス時期を定める際に考慮しなければならない要素としては、装置やシステム面から見た場合は、対象となる装置の重要度や、要求される信頼度などがあり、リレーから見た場合は、特性または項目ごとの故障形態があります。
リレーの故障形態は、大きく分けて接点の消耗などに代表される摩耗形態の故障と、コイル巻線のレヤショートに代表される劣化形態の故障とがあります。
一般的に使用するリレーの形式使用条件が決まると、接点の消耗などの摩耗形態や故障時期は動作回数に沿ったものとなり、事前に予測の立つことが多いですがこれに対してコイル巻線のレヤショートなどの劣化形態の故障は、使用されるリレーの持つ固有信頼性に大きく影響します。一方では、使用条件や現場環境などの使用信頼性の影響を受けて使用時間に沿ったものとなります。
したがって個々の事例ごとに異なったものとなることも多く、事前予測を立てにくいことが多いようです。
さらに実使用上では、摩耗と劣化は並列で進行するので、どちらの形態の故障が早く現れるかを知ることはメンテナンス時期を定める上での重要な要素となってきます。
メンテナンスの時期を決めるため、参考となる項目を以下に示します。
| メンテナンスの時期 | 回数 軸系 | 時間 軸系 | 備考 | ||
| 摩 耗 | 接点の摩耗 | 負荷電圧、電流、負荷の種類から電気的耐久性 曲線でメンテナンス時期を求める。 適合する電気的耐久性曲線がない場合は 実機による実験値からメンテナンス時期を決める。 | ○ | ― | 所定時間内の 開閉回数が 定まれば時間軸に 置き換えが可能。 |
| 動作機構部の摩耗 | 機械的耐久性回数によりメンテナンス時期を求める。 ただし、性能に示される機械的耐久性回数は 標準試験状態下の値であり、使用条件が この条件に異なる場合には、実用条件下での 実験値をもとにメンテナンス時期を決める。 | ― | |||
| 劣 化 | コイルおよびコイル 巻線の絶縁劣化 | コイルの実用条件下での温度を知ることにより、 耐用時間を予測する。 通常ポリウレタン銅線の場合120℃、 40,000時間を基準点にとることが多い。 | ― | ○ | ― |
| 接点の接触安定度 | 固有信頼性を基礎に、使用条件、環境雰囲気の 影響を受けて大幅に変化する。 使用条件、環境雰囲気の状態を把握しながら サンプリングなどにより、メンテナンスの時期を決める。 | ― | ○ | 現場雰囲気、接点材料 に悪影響を与える 悪性ガス濃度などを 把握しておく必要あり。 | |
| 金属材料の性能劣化 | |||||
| 樹脂材料の性能劣化 | |||||
メンテナンスの目安
機械的耐久性
接点は無負荷でコイルに定格電圧(AC操作においては定格周波数)を加え、定格開閉ひん度で動作させたときの外観および特性の変化を見ます。
電気的耐久性
耐久性に達したかの判断は使われ方によって違います。
耐久性判定の目安
| 判定項目 | 規定値 | ||
| 外観 | 各部分の緩み、変形、損傷がないこと | ||
| 絶縁抵抗 | 特に規定がない限り1MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | 初期規格値の75%以上 | ||
| コイル抵抗 | 初期規格下限値の95%から初期規格上限値の105%まで | ||
| 動作電圧 | 初期規格値の1.2倍以下 | ||
| 復帰電圧 | 初期規格値の0.5倍以上 | ||
| 動作時間 | 初期規格値の1.2倍以下 | ||
| 復帰時間 | 初期規格値の2倍以下 | ||
| 接触抵抗 | 接点定格電流 または開閉電流(A) | 測定電流 (A) | 接触抵抗試験後 (Ω) |
| 0.01未満 | 0.001 | 100 | |
| 0.01以上~0.1未満 | 0.01 | 20 | |
| 0.1以上~1未満 | 0.1 | 5 | |
| 1以上 | 1 | 2 | |
JIS C5442による
-
 PDF版をダウンロード 6682KB
PDF版をダウンロード 6682KB
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.




 マイカタログに追加
マイカタログに追加 Facebook
Facebook