使用する設備の条件により適切な機種を下表より選択してください。
K2GS-B
地絡方向継電器(ZPD方式)

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
- 特長
- 形式/種類
- 定格/性能
- 外形寸法
- ご使用の前に
- カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア
情報更新 : 2024/01/23
安全上の要点
継電器本体

零相電圧検出装置
・形VOC-3S、形VOC-1MS2は前出の定格のように、非常に小容量(高インピーダンス)のため、接地補償用コンデンサの代役は務められません。接地補償用コンデンサなどを使用してください。
・形VOC、しゃ断器、ZCT などの相互関係位置は継電器の方向性とは関係ありませんが、通常は母線に設置してください。
ZCTの位置は特に保護範囲に直接関係しますが、電力会社で設置位置を推奨している場合がありますので、設置の際には必要に応じて電力会社とご相談ください。
絶縁変圧器がある場合
受電設備に絶縁変圧器がある場合は、接地補償用コンデンサなどをご使用ください。
・特別高圧系統から受電し6,600Vあるいは3,300Vに降圧(6,600V/3,300Vの降圧を含む)して構内配電されているところでは受電設備に変圧器が入っています。
この場合、変圧器から零相変流器までの対地容量は非常に小さく、しかも電力会社の配電線からも絶縁されてしまうため、地絡事故時には地絡電流が流れず、継電器は動作不能となります。
・その対策上、変圧器と零相変流器設置点の間に対地静電容量を接続する必要がありますので、その場合には接地補償用コンデンサなどをご使用ください。
なお、接地は第1種接地とし、継電器の整定値は0.4A以下にしてください。
ラッシュ電流
ラッシュ電流が考えられる場合は、定格電流の大きな零相変流器をご使用ください。
・ラッシュ時には数倍から10数倍の電流が数サイクル以上流れ、残留電流を生じて継電器の動作に影響をおよぼしますので、定格電流の大きな零相変流器を使用してください。
・形K3P-M 単品試験等はN 端子への配線を必ず開放してください。
・コンデンサ高圧端子配線時はケーブル被覆を必ず剥離してください。
接地
①各機器の接地種別
電気設備技術基準第19条の接地線の太さに対して十分余裕のある電線を使用して、確実に接地してください。
お願い
形VOC の接地端子の接地は第1 種接地とし、受電設備の他の第1種接地配線と接続してください。
形VOCのY2端子、ZCTなどは第3種接地とし、他の第3種接地配線と接続して1点接地としてください。
形K2GSのケースアースは第3種接地とし、直接接地母線へ配線するか、または継電器のY2端子へ配線することにより、間接的に接地母線へ接続されるようにしてください。
注. E(ケースアース)はR2ケースにはありません。
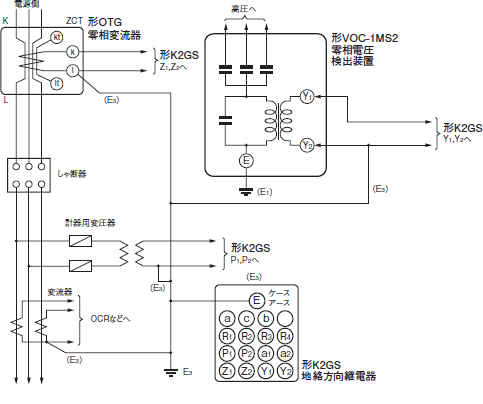
注. E1、E3はそれぞれ第1種接地、第3種接地を表わします。
②高圧ケーブルのシールドの接地例と機能(高圧受電設備指針より引用)
・引込用ケーブル 負荷側ケーブルヘッドにて1点接地
この場合、ケーブルの地絡故障検出が可能ですが、CBが負荷側のため故障箇所のしゃ断保護はできません。
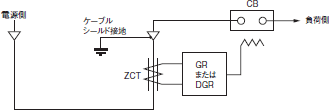
・引出用ケーブル 電源側ケーブルヘッドにて1点接地
ケーブルの地絡故障検出が可能で、電源側CBのために、ケーブル地絡故障しゃ断ができます。
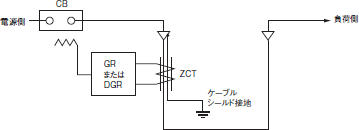
・引出用ケーブル 負荷側ケーブルヘッドにて1点接地
ケーブルの地絡故障検出が可能で、電源側CBのためケーブル地絡故障しゃ断が可能です。
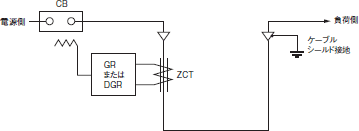
・引込用ケーブル 両端電源側接地
ケーブルの地絡故障検出はできません。
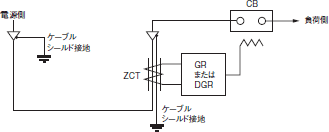
・引出用ケーブル 両側負荷側接地
ケーブルの地絡故障検出が可能で、電源側CBのためケーブル故障のしゃ断が可能です。
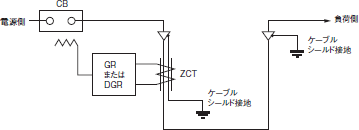
配線
・零相変流器ZCTの試験端子kt、ltは試験時のみに使用し、試験後は開放しておいてください。
また、盤表面に試験端子を設けておくと、保守上便利です。
・継電器に接続しない場合は、ZCTのk、l端子は必ず短絡しておいてください。
・ZCT 2次側の配線の際は誘導障害にご注意ください。
・しゃ断器の引きはずしコイルは、接地側でない方を継電器のa接点端子側に接続してください。
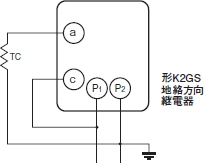
・ZCTとトリップ回路の配線に(4芯コード等の)同一ケーブルは使用しないでください。
・電線の耐久性、絶縁性への影響を少なくし、長時間事故なくご使用いただくため、ZCTの貫通電線については次の点に
ご注意ください。
曲げの限界Rは下表のとおりです。
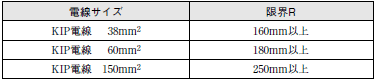
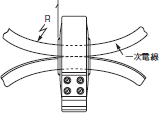
使用環境について
・標高2,000m以下でご使用ください。
・異常な振動、衝撃、傾斜のない状態でご使用ください。
・有害な煙やアンモニア等のガス、爆発性のガス、過度の湿気、水滴や蒸気、塵埃や風雨にさらされる状態での使用をさけてください。
・塵埃、鉄粉等のある場所ではケースを開かないようにしてください。
・湿気、塵埃の少ない場所に保管してください。
使用上の注意
組み合わせ零相変流器
当社の下記零相変流器との組み合わせであれば、いずれの製造番号のものでも使用可能です。
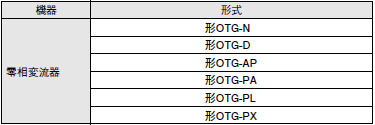
継電器の零相電圧整定と公称動作値の関係
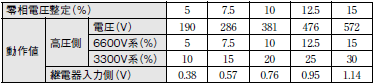
誘導障害対策
零相変流器 形OTGと継電器間、零相電圧検出装置と継電器間を各々結ぶ信号線は、微弱な信号の受け渡しをしますので誘導の影響を受けやすくなります。配線の際には次の点に注意し、必要な対策を実施してください。
①静電誘導障害と対策
零相変流器と継電器間、零相電圧検出装置と継電器間の配線が10mを超えますか?
超える場合、静電誘導障害を受けるおそれがあります。
対策として、シールド線を使用してください。
・大地から絶縁されているA、B 2本の電線があってA線に交流の高圧が加わっている場合、A-B間の静電容量C1とB-大地間の静電容量C2により、B線にはC1、C2で分圧された電圧が誘導されます。
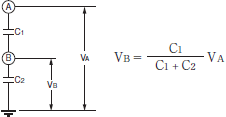
6kVケーブルの場合は芯線の周囲にしゃへい層があって、これが接地されますのでB線は誘導を受けません。
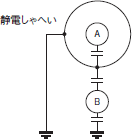
・しゃへい層のない3kV ケーブルが10m 以上にわたって並行する場合は、B線にはシールド線を使用し、しゃへい層を接地してください。
・常用使用状態において配電系統の残留分により、零相電圧検出LEDが常時点灯状態となるような整定でのご使用は避けてください。
②電磁誘導障害と対策
零相変流器と継電器間、零相電圧検出装置と継電器間各々の配線が、高電圧線、大電流線、トリップ用配線などと接近し、並行しますか?
その場合、電磁誘導障害を受けるおそれがあります。
対策として、障害を受ける配線を他の配線から隔離し、単独配線としてください。
・A、B両線が近接している場合、A線に電流が流れると、右ねじの法則による磁束が生じ、B線に誘導電流が流れます。低圧大電流幹線をピット・ダクトなどで近接並行して配線する場合にはこの現象が顕著なため注意が必要です。
・電磁誘導障害を防止するためA-B間を鉄板でおおうか、B線を電線鋼管に入れるなど、両電線間を電磁的にしゃへいしなければなりません。A線と逆位相の電線が近接していたり、2芯以上のケーブルのようにより合わせてある場合は影響は少なくなります。数百アンペアの幹線において、各相の電線と信号線が10cm以内に近接し、かつ10m以上並行している場合にはこの対策を必要とします。
③誘導障害の判定方法
・継電器の電流整定値を0.1Aに整定し、Z1-Z2間をデジタルボルトメータ、真空管電圧計またはシンクロスコープで測定してください。5mV以上あれば対策が必要です。(継電器の動作レベルは約10mV)
・また電圧整定値を5%に整定し、Y1-Y2間に上記の測定器を接続して200mV以上あれば対策が必要です。ただし、残留分の場合もありますので、シンクロスコープにて波形を観測することをおすすめします。(残留分の場合は普通の正弦波、誘導の場合にはそれ以外の波形が観測されます)
形K2GS-B地絡継電器
試験スイッチによる試験方法
(零相変流器と組み合わせて試験する必要はありません。)
① 制御電源端子P1、P2間にAC110Vを印加してください。
② 試験スイッチを押してください。
③ 動作表示部がオレンジに変わり接点が動作します。
注. 復帰方式による接点動作は下記の通りです。
自動復帰の場合:動作時間のみON
手動復帰の場合:復帰レバーを押すまでON
④試験後ケース前面右下の復帰レバーを押し上げ、復帰させてください。(この試験スイッチは継電器内部の回路が正常であるかをチェックするためのもので、周辺機器および配線のチェックではありません。)
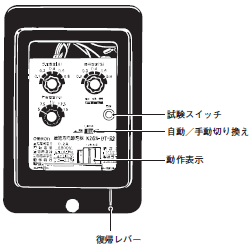
現場での動作特性試験
現場での動作電流試験配線図、動作時間試験配線図、試験方法と判定基準を下記に示します。
・本試験を行う場合、主回路は必ず停電していることを確認の上、実施してください。
・下記試験回路例は市販のDGR試験装置を使った事例です。市販の試験装置の取扱いについては各試験機メーカーへお問い合わせください。
動作電流・動作電圧試験配線図
動作電流・動作電圧 判定基準
JIS C 4609 高圧受電用地絡方向継電器に準じます。
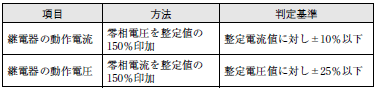
零相電圧の整定タップと零相電圧値
零相電圧の整定タップは完全地絡継電圧を100%とした整定タップとなっています。
(例)6.6kV配電系統の場合
完全地絡電圧=6600/√3≒3810V
「この値が100%に相当します。」
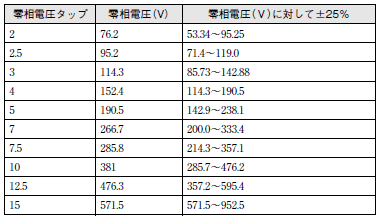
動作時間試験配線図
試験条件・判定基準
形VOC-1MS2 零相電圧検出装置
動作確認
形K2GS-Bが動作範囲に入らない場合は、原因を切り分けるために形VOC-1MS2 零相電圧検出装置単体でのご確認をお願いいたします。
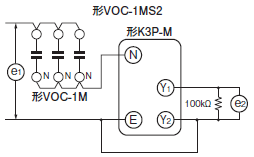
① 高圧端子3本を短絡してください。
② 高圧端子一括とE(アース)端子間にAC190.5V、AC381V、AC571.5V各々を印加します。
③ 出力電圧Y1-Y2間の電圧を測定してください。公称出力電圧は下表となります。
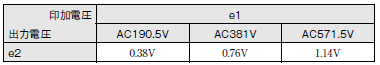
テスト入力端子からの試験
形K3P-M 零相電圧変換器にはテスト入力端子があり、これによって試験することもできます。
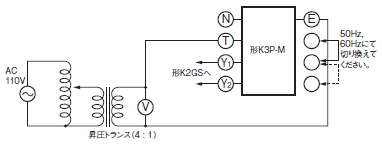
この試験回路における零相電圧の公称動作値は次のとおりです。
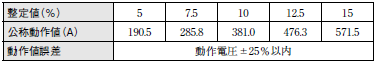
形OTG-D 分割形零相変流器
・継電器との接続は次の通りに行ってください。k、端子の片 側を短絡板で接続してください。次にもう片方のkから継電器のZ1、からZ2に接続してください。
・ケーブルの芯線部がOTG に触れることのないよう、ケーブル絶縁部に貫通させてください。
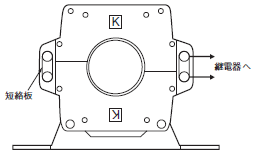
・分割形の試験端子は、オプションとなります。注文の際には、 下記形式で手配ください。
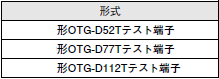
また、ZCTのKからLに向かって試験電線をあらかじめ貫通して設置しておくこともできます。この場合、試験電線は600V 以上の絶縁電線を使用し、機械的ストレスが加わらないようにしておくことが必要です。
取りつけ方法
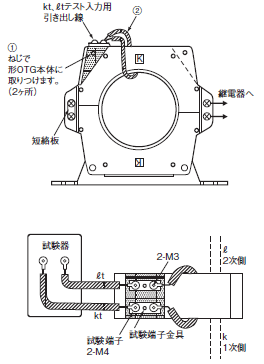
① 試験端子をM4× 10ねじで変流器本体に取りつけてください。
(両サイド2本必要)
② 付属電線を変流器本体へ1 回貫通させて上面の取りつけねじ部に取りつけてください。
総合試験
図のような回路では、高圧をかけたままの状態で押ボタンスイッチ(PBS)により、しゃ断試験が行えます。図のR1に5Ω(10W以上の容量)、R2に100Ω(200W以上の容量)を使用すれば、継電器のY16とY2端子間には5V程度の電圧が加わり、ZCTには1A程度の電流が流れます。
(試験用回路の配線を長くすると、誘導などにより継電器の動作に悪影響をおよぼしますのでご注意ください)
情報更新 : 2024/01/23




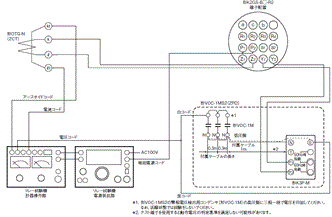
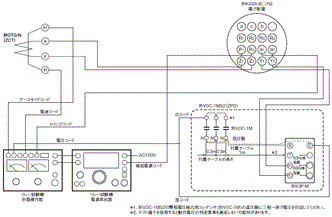
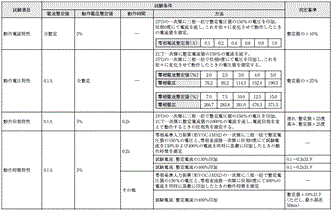
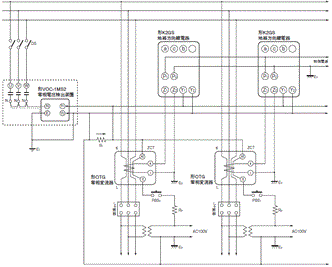
 Facebook
Facebook