常規使用状態において配電系統の残留分により、零相電圧検出LEDが常時点灯状態となるような整定でのご使用は避けてください。
K2GS-H
デジタル形地絡方向継電器(ZPD方式)

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
- 商品カテゴリ共通
- 特長
- 形式/種類
- 定格/性能
- 外形寸法
- ご使用の前に
- カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア
情報更新 : 2024/01/23
使用上の注意
形K2GS-H地絡継電器
試験スイッチによる試験方法
(零相変流器と組み合わせて試験する必要はありません。)
① 制御電源端子P1、P2間にAC110Vを印加してください。
② 試験スイッチを押してください。
③ 動作表示部がオレンジに変わり接点が動作します。
注. 復帰方式による接点動作は下記の通りです。
自動復帰の場合:動作時間のみON
手動復帰の場合:復帰レバーを押すまでON
④ 試験後ケース前面右下の復帰レバーを押し上げ、復帰させてください。(この試験スイッチは継電器内部の回路が正常であるかをチェックするためのもので、周辺機器および配線のチェックではありません。)
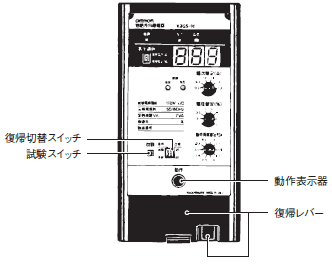
現場での動作特性試験
現場での動作電流試験配線図、動作時間試験配線図、試験方法と判定基準を下記に示します。
・本試験を行う場合、主回路は必ず停電していることを確認の上、実施してください。
・下記試験回路例は市販のDGR試験装置を使った事例です。市販の試験装置の取扱いについては各試験機メーカーへお問い合わせください。
動作電流・動作電圧試験配線図
動作電流・動作電圧 判定基準
JIS C 4609 高圧受電用地絡方向継電器に準じます。

零相電圧の整定タップと零相電圧値
零相電圧の整定タップは完全地絡継電圧を100%とした整定タップとなっています。
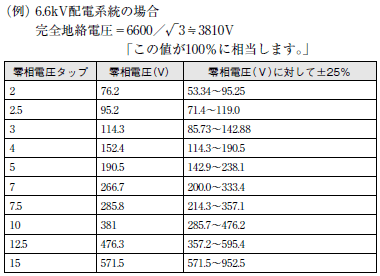
動作時間試験配線図
試験条件・判定基準
形VOC-1MS2 零相電圧検出装置
動作確認
形K2GS-Hが動作範囲に入らない場合は、原因を切り分けるために形VOC-1MS2 零相電圧検出装置単体でのご確認をお願いいたします。
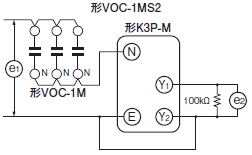
① 高圧端子3本を短絡してください。
② 高圧端子一括とE(アース)端子間にAC190.5V、AC381V、AC571.5V各々を印加します。
③ 出力電圧Y1-Y2間の電圧を測定してください。公称出力電圧は下表となります。
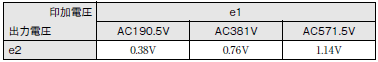
形OTG-D 分割形零相変流器
・継電器との接続は次の通りに行ってください。k、ℓ端子の片側を短絡板で接続してください。次にもう片方のkから継電器のZ1、ℓからZ2に接続してください。
・ケーブルの芯線部がOTG に触れることのないよう、ケーブル絶縁部に貫通させてください。
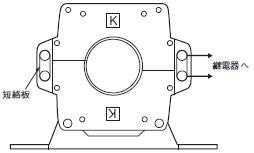
・分割形の試験端子は、オプションとなります。注文の際には、下記形式で手配ください。
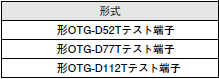
また、ZCTのKからLに向かって試験電線をあらかじめ貫通して設置しておくこともできます。この場合、試験電線は600V以上の絶縁電線を使用し、機械的ストレスが加わらないようにしておくことが必要です。
取りつけ方法
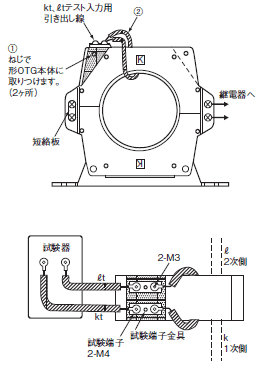
① 試験端子をM4×10ねじで変流器本体に取りつけてください。(両サイド2本必要)
② 付属電線を変流器本体へ1 回貫通させて上面の取りつけねじ部に取りつけてください。
保守・点検
特に点検は不要ですが、年に1~2回の定期点検をおすすめします。
動作値誤差が著しく大きい場合については、微調整ボリュームにより調整を行ってください。
なお、社団法人 日本電機工業会の「保護継電器の保守・点検指針」(JEM-TR 156)で保護継電器に関して詳しく掲載されていますので、その活用をおすすめします。
微調整ボリューム
情報更新 : 2024/01/23
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.




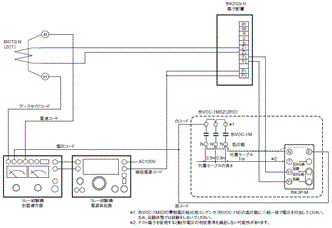
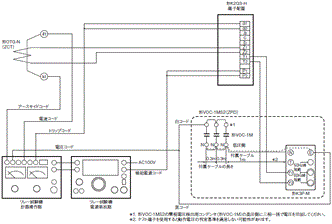

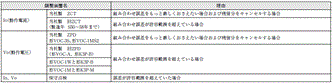
 Facebook
Facebook